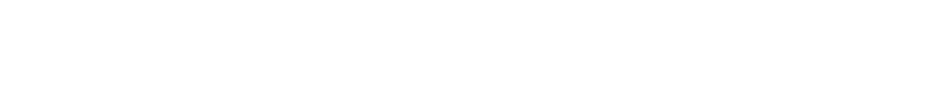LOCAL PRIDE vol.3
バイヤー武石が訪ねた
岡山県・倉敷
日本各地に受け継がれる文化や伝統。
LOCAL PRIDEでは、その地域ならではの魅力を発信しています。
3回目となる今回は、岡山・倉敷のデニムを中心に、バイヤーが出会った素敵なヒト・モノ・コトをご紹介します。

『3rd STYLE』
バイヤー 武石
大阪・東京を渡り歩き、担当したアイテムはドレスアイテムからヴィンテージやアートまで幅広い。現在は、『3rd STYLE』バイヤーとして、こだわり抜かれた品物とスタイリングをお客様にご提案。
倉敷といえば、やはりデニム

倉敷は、元々帆布の産地として栄え、厚手の生地を生産・加工する技術が発展していきました。その後、デニムブームが起こり、海外からの仕入れだけではなく、国内でも織り始めたことが“倉敷=デニム”として認知されるようになるきっかけでした。

海外メゾンブランドをはじめ、国内外に1,000社以上、世界20ヵ国へと生地を販売している「ジャパンブルー」。多数の生地を取り扱っており、正確にカウントできないほど。生地には、それぞれ特性に合った生産地があり、そこから収集するようにしているのだとか。

担当者である森田さんにデニムの良し悪しについて聞いてみると、「デニムは個人の好みが特に分かれるので、一概に良いというものはなく、自分の好みに合った表情の生地を選んでもらえれば」とのこと。ぜひ自分好みのデニムを選ぶ参考にしてみてください。
Jimba‘s(ジンバズ)

5年前に関東から倉敷に移住した「Jimba’s」の代表、陣場泰裕さん。大学在学中に並行して縫製を学び、オーダースーツ店やアパレルブランドで働いた後、海外へ。フィリピンやオーストラリアで働く中で、“日本の良い産業を海外へ持っていきたいという気持ち”が芽生えたのだとか。中でも、自身がシンプルで長く使えるものが好きであったことから、デニムに強く惹かれるように。倉敷にて2年半の修業を経て独立し、オーダーデニムブランド「Jimba’s」を本格的にスタートさせました。

「長く使われるものをひとつずつ丁寧に作りたいという気持ちと、前職からの知識・経験を生かす方法としてオーダーデニムにたどり着きました。」
ブランドの拠点に倉敷・児島を選んだのは、“デニムの本場”といわれる場所に身を置きたいと思ったから。コミュニティが狭いからこそ、近くに同業者がたくさんいて、すぐに相談できるのもこの地ならでは。今実際に使用しているカンヌキと巻き縫いミシンは、同業者からいただいたものだそう。

「Jimba’s」のデニムの魅力は、セルヴィッチの風合いと、デニムの良さを残しつつ、綺麗に見せるシルエット。綺麗だけど温かみがあって、愛着を持ってずっと履けるものを目指しています。

「岡山の方が若くしてブランドを立ち上げる例もあるが、自分でデザインをして作っている職人はほとんどいないんです」と語る陣場さん。特に、オーダーデニムを行っている人は都会にしかいないそうで、自分がその道を示していくんだという意気込みを感じました。
髙田織物

全国の8割の生産を誇る畳縁産業の地、児島。「髙田織物」は、初代の髙田徳太郎が個人創業して以来、現在の6代目に至るまで一族経営を続けています。児島の名産であった真田紐(細幅の織物)の製造を唐琴地区で始めたことが創業のきっかけ。織りにこだわる精神は創業当初から変わらず、伝統を守りながらも、新しい畳縁を模索し、生み出し続けています。

畳縁の存在と魅力を伝えるために作られたのが、直営店である「FLAT」。長さが短い畳縁や余った畳縁を廃棄するのではなく、ハンドメイドの素材として販売しています。畳縁が軽くて丈夫、そして種類も豊富にある織物であることを伝えていくことは、畳縁の可能性を広げることにも。
「ただ作るではなく、短くても意味のある織物へと昇華することで、趣味の時間も豊かに」
これは、「髙田織物」が大切にしている考え方です。

今回はそんな端材を使って作られたポーチやコインケースなどの小物も販売。畳が私たちの部屋を彩ってくれるように、畳縁からできた雑貨は私たちの暮らしを彩ってくれるはずです。

倉敷帆布

次に訪れたのは、帆布の生産を135年近く行う「倉敷帆布」。その昔、瀬戸内海は島の集まりだったことから、お米が作れず、塩害に強い綿花栽培が盛んだったそう。倉敷の温暖な気候と糸を紡ぐ・撚る・染めるといった技術が根付いていたことから、江戸末期には、厚手綿織物の産地として大きく栄えることになりました。

しかし、年々生産者が減っており、倉敷の生産工場はここだけ。
なんとしても、この地で生まれた素材を残していきたいという想いから、生産を続けています。

「倉敷帆布」には国内に400台しかない旧式のシャトル織機が60台現存しています。効率の良い新しい機械はなく、全て昔の機械のみで生産。1日に50m程しか織れないため、効率は悪いが、その分空気をはらんでふんわりとした、温かみのある表情の生地に仕上がります。

船室の素材やエレベーターのベルトの芯など、強度の必要なものを制作するのはもちろん、トートバックやポーチなども制作。その裾のを広げようと奮闘中。今年は就職サイトにも掲載した効果から、地元の若い方が4名入社。「この産業をこれからまた100年続けていこう」という気持ちで、機械を動かし続けています。
ふなおワイナリー
最後に、「ふなおワイナリー」へ立ち寄ってみました。育てる手間が非常にかかることなどから生産者が減っていた“マスカット・オブ・アレキサンドリア”を引き継いでいきたいという思いからワイナリーを創業。

ボランティアによってポイントが貯まり、そのポイントをワインやぶどうと交換する仕組みを整えて、地域の人たちと二人三脚で生産を続けています。

ぶどうそのものを食べているような香りとフレッシュな甘さが、ここで造られるワインの特徴。地元で栽培される“マスカット・オブ・アレキサンドリア”を守っていきたい、その魅力を多くの人に知ってもらいたいという思いを胸に、今日もワインを造っています。

生産者の減少や海外からの輸入品の影響など、逆風に吹かれる機会も多い中、それでも自分たちのものづくりを信じて、未来につなげていこうとする姿に“LOCAL PRIDE”を感じました。