
スイーツ&グルメ2022/4/25 更新
お酒にはどんな種類があるの?醸造酒・蒸留酒・混成酒の違いや特徴とは
世界にはどんなお酒があるのかご存じですか?ビールやワインをはじめ、ブランデー、ラム、テキーラなど数えきれないほどの種類がありますよね。この記事では、醸造酒・蒸留酒・混成酒の3つに分けてお酒の種類を詳しく解説。「今飲んでいるものとは別の種類のお酒について知りたい」「お酒の知識を深めて楽しみ方を広げたい」そんな方は必見です♪
お酒の種類をわかりやすく解説!

ワイン、ビール、ウイスキー、ブランデーなど、世界には数えきれないほどたくさんのお酒がありますよね。じつはこれらのお酒は、製造方法によって「醸造酒(じょうぞうしゅ)」「蒸留酒(じょうりゅうしゅ)」「混成酒(こんせいしゅ)」の3つに大別することが可能。この3つを覚えると、お酒全体の構造が理解しやすくなりますよ。
本記事では、醸造酒、蒸留酒、混成酒の定義やそれぞれの特徴をもとに、お酒の種類を詳しくご紹介します!
「醸造酒」の定義と特徴
果物や穀物を原料とし、酵母を加えて発酵させて造るお酒を「醸造酒」と言います。醸造酒、蒸留酒、混成酒のなかで製造方法がもっともシンプルで、一番長い歴史をもつのが醸造酒。
酵母を加えてアルコール発酵させる「単発酵酒(ワイン)」と、デンプンを糖に分解してから酵母を加えて発酵させる「単行複発酵酒(ビール)」、糖化と発酵をひとつのタンクで同時におこなう「並行複発酵酒(日本酒)」の3つが代表的です。
醸造酒の種類は?おすすめのお酒も!
世界最古のお酒といわれる「ワイン」

原料に酵母を加えるだけの「単発酵」という発酵方法で造られるのがワインです。ワインの原料であるブドウにはもともと糖分が含まれているため、酵母を加えるだけでアルコール発酵させられるのが特徴。諸説ありますが、ワインを含む果実酒がお酒の起源とも言われているんですよ。
ワインには果汁、皮、種を一緒に発酵して造る「赤ワイン」と、果汁だけを発酵して造る「白ワイン」の2種類があります。
丹波ワイン 小式部 赤・白ワインセット

ワイン初心者の方からツウの方まで、幅広い人におすすめしたいのがこちら。和食に合うよう作られた、京都産のワインの2本セットです。白ワインは酸味のあるブドウと糖度の高いブドウがバランスよくブランドされており、飲みやすい味わい。甘さは控えめで、和食だけでなくさまざまな料理にマッチします。
赤ワインは上品な果実香とほどよい酸味が特徴。渋みは控えめで、肉料理や赤身の魚とよく合いますよ。
詳しく見る >
世界中で大人気!「ビール」

世界各国で造られている大人気のアルコール「ビール」。ワインの次に長い歴史をもつとされるお酒です。ビールの主な原料は「麦芽(モルト)」。麦芽はそのままではアルコール発酵しないため、まず粉砕してお湯と混ぜ、デンプンを糖にする(糖化)ことから始まります。これがワインの製造方法と大きく異なる点です。
ビールは発酵方法によって「エール」と「ラガー」の2種類に大別されています。エールとは「上面発酵」で造られるビールのこと。昔ながらの製造方法で、麦汁(※)の表面に酵母が浮いてくるため「上面」と呼ばれています。
ラガーは「下面発酵 」で造られるビールのこと。上面発酵とは逆に酵母がタンクの底に沈んでいくので「下面」と呼ばれています。中世以降から始まった造り方で、雑菌が繁殖しにくく管理しやすいのが特徴。現在世界で流通するビールの多くは、ラガーの一種である「ピルスナー」というスタイルです。
※麦汁(ばくじゅう)......糖化した麦芽をペースト状にし、ろ過したもの
日本を代表するお酒「日本酒」

「日本酒」は、米や米こうじを主な原料とする日本古来のお酒です。ワインやビールと同じ醸造酒に分類されますが、発酵方法が少し複雑。前述したようにビールは「糖化」と「発酵」を順番におこなうのに対して、日本酒はこの2つがひとつのタンク内で同時におこなわれるのが特徴です。
日本酒はお米の精米歩合(玄米を削り残った割合)によって8種類に分類されています。
・本醸造酒(ほんじょうぞうしゅ)......米、米こうじ、醸造アルコールを主な原料とする精米歩合70%以下のお酒。すっきりとした味わいが特徴
・特別本醸造酒(とくべつほんじょうぞうしゅ)......米、米こうじ、醸造アルコールを主な原料とするお酒。精米歩合60%以下、または特別な製法を用いて造られる。クリアな味わいが特徴
・吟醸酒(ぎんじょうしゅ)......米、米こうじ、醸造アルコールを主な原料とする精米歩合60%以下のお酒。華やかな香りと繊細な味わいが特徴
・大吟醸酒(だいぎんじょうしゅ)...... 米、米こうじ、醸造アルコールを主な原料とする精米歩合50%以下のお酒。吟醸酒より雑味が少なく、繊細な味わいが特徴
・純米酒(じゅんまいしゅ) ......米、米こうじを主な原料とするお酒。精米歩合の規定はなし。濃厚な味わいのものが多い
・純米吟醸酒(じゅんまいぎんじょうしゅ)...... 米、米こうじを主な原料とする精米歩合60%以下のお酒。ほんのりとお米の甘みを感じる味わい
・純米大吟醸酒(じゅんまいだいぎんじょうしゅ)......米、米こうじを主な原料とする精米歩合50%以下のお酒。雑味がなく、お米の甘みやコクを感じられる
・特別純米酒(とくべつじゅんまいしゅ)...... 米、米こうじを主な原料とするお酒。精米歩合60%以下、または特別な製法を用いて造られる。上品なお米の旨みを感じられる
三重県(大田酒造) 大吟醸 半蔵 伊賀山田錦

「日本酒は種類がありすぎて何を選べば良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか?そんな方には、数々の受賞歴を持つ人気の日本酒「大吟醸 半蔵 伊賀山田錦(だいぎんじょう はんぞう いがやまだにしき)」がおすすめです。
商品名の通り三重県・伊賀産の山田錦を100%用いて造られたお酒で、華やかな吟醸香とやや辛口のすっきりとした味わいが魅力。プレゼントにも喜ばれる一本です。
詳しく見る >
「蒸留酒」の定義と特徴
原料を発酵させ、さらに蒸留した飲み物を「蒸留酒」と言います。簡単に説明すると、醸造酒を蒸留したものが蒸留酒。蒸留とは液体を加熱して気体にしてからもう一度液体に戻す作業のことで、これによって蒸留酒は醸造酒よりもアルコール度数が高くなる特徴があります。
蒸留酒は、ウイスキー、ブランデー、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、焼酎の7種類が代表的。蒸留方法は「単式蒸留」(一度だけ蒸留をおこなう昔ながらの製法)と、「連続式蒸留」(ウイスキーのために開発されたとされる、何度も蒸留をおこなう近代的な製法)の2種類に大別されています。
蒸留酒の種類は?おすすめのお酒も!
ウイスキー

「ウイスキー」は主に大麦を原料とするお酒です。端的に説明すると、ビールを蒸留したものがウイスキー。アルコール度数は40度ほどで、ロックやストレートで飲むほか、炭酸で割ってハイボールにして味わうのも人気があります。
ウイスキーは代表的な産地が5つあり、この産地で作られたものは「5大ウイスキー」と呼ばれているのが特徴。原料や製法が異なるため、それぞれに個性があります。
・スコットランド(スコッチ・ウイスキー)......大麦麦芽を主原料とするウイスキー。製造の際に使われるピート(炭化した泥炭)の独特な香りをもつものが多い
・アイルランド(アイッリッシュ・ウイスキー)......大麦麦芽を主原料に、ライ麦や小麦も使われることが多いウイスキー。まろやかで飲みやすいものが多く、初心者向きとされている
・アメリカ(アメリカン・ウイスキー)......ライ麦、とうもろこし、小麦、大麦などを混合して造られるウイスキー。香り・味ともにクセが強いものが多いのが特徴
・カナダ(カナディアン・ウイスキー)......ライ麦を主原料に、小麦、大麦、とうもろこしなども使われることが多いウイスキー。ライトな味わいのものが多く、日本食との相性も良いとされている
・日本(ジャパニーズ・ウイスキー)......大麦麦芽を主原料とするウイスキー。日本人の好みに合わせて、クセがなく飲みやすいものが多い
産地のほか、原料による分類方法も。大麦麦芽を原料とするものを「モルトウイスキー」、とうもろこしや小麦を主原料とする「グレーンウイスキー」、これらをブレンドしたものを「ブレンデッドウイスキー」と言います。
ベンロマック シングルカスク 2008年 Specially Selected for Japan

いつもと違う銘柄のウイスキーを楽しみたい方におすすめの一本がこちら。スコットランドの「ベンマロック蒸留所」で造られた、スペイサイドシングルモルトのスコッチウイスキーです。日本のファンに向けてリリースされた特別モデルで、はちみつのようなまろやかな甘さと、独特のピート香が楽しめます。
詳しく見る >
ブランデー

ブランデーはブドウやりんごなどの果実をアルコール発酵させ、それを蒸留して造るお酒です。もともとブドウを原料としたものを指していましたが、現在では果実を主原料とする蒸溜酒全般をブランデーと呼びます。ワインと同じく、フランスのコニャック地方で造られるものが特に有名です。
ブドウ以外に、りんごが原料の「カルヴァドス」、さくらんぼが原料の「キルシュワッサー」なども。ウイスキーとブランデーは見た目がよく似ていますが、原料が違うので味わいはまったく異なります。
ジン

ジンは大麦、ライ麦、ジャガイモなどを原料とする蒸留酒です。無色透明で、カクテルの材料として使われることが多いのが特徴。見た目はお水のようですが、香草や薬草で香味付けされるため独特の風味があります。
飲み方は、トニックウォーターで割る「ジン・トニック」が定番。もちろんストレートやロックで楽しむこともできます。
ヘンドリックス ジン44゜

定番のジンとはひと味違うものをお探しなら、こちらの一本はいかがですか?スコットランドのヘンドリックス蒸留所で少量のみ造られている、プレミアムな味わいのジンです。11種類の香草や薬草のほか、バラの花びらやきゅうりのエキスが使われているのが特徴。柑橘類やミントを思わせるさわやかな香りで、飲み口はとってもなめらかです。一度飲んだらクセになる味わいですよ。
詳しく見る >
ウォッカ

とうもろこしや大麦、じゃがいもなどを原料とした蒸留酒を「ウォッカ」と言います。無色透明の見た目はジンとそっくりですが、ウォッカは白樺の炭でろ過して造られるのが特徴。またジンはボタニカル(香草や薬草)の風味がするのに対し、ウォッカはクセのない味わいです(香り付けされた「フレーバーウォッカ」もあります)。
ジン、ウォッカ、ラム、テキーラの4つは「4大スピリッツ」と呼ばれ、主にカクテルの材料として使われています。
ラム

ラムは、サトウキビの絞り汁からできる「糖蜜」を原料とする蒸留酒です。原料からも分かるように、濃厚な甘みがあるのが特徴。ラムは原料や製造方法によって「ヘビーラム」「ライトラム」「ミディアムラム」の3つに分類されています。
・ヘビーラム......見た目は濃い褐色で、コクと香りが強いのが特徴
・ライトラム......やわらかな味わい。見た目は無色または淡い黄色
・ミディアムラム......ほどよく個性がある、ヘビーラムとライトラムの中間の味わい
クセの強いヘビーラムは、お菓子作りにもよく使われています。ライトラムやミディアムラムは、カクテルベースとして楽しむのが人気です。
セイラージェリー 40゜ スパイスド ラム

カクテルベースとしても使いやすい、なめらかな味わいのラムです。バニラやキャラメルのような甘さに、シナモンやナツメグの香りがアクセント。それほどクセがなく飲みやすいので、そのままロックで飲んだり、カクテルベースにしたり、製菓用にしたりと幅広く楽しめますよ。
アメリカの人気タトゥーアーティスト、ノーマン"セイラー・ジェリー"コリンズが好んで飲んでいたラムを再現して作られています。
詳しく見る >
テキーラ

テキーラは、メキシコ原産の植物「竜舌蘭(りゅうぜつらん)」の一種である、「アガヴェ・アスール・テキラーナ・ウェーバー」の茎を原料とする蒸留酒です。原産地呼称が認められており、メキシコの決められた場所以外で造られたものは「テキーラ」と名乗ることはできません。樽熟成の期間の長さによって、4つに分類されています。
・ブランコ......樽熟成していないもの、または樽詰めして60日未満のもの。無色透明でほのかに甘みがあるのが特徴
・レポサド......2ヶ月〜1年未満の樽熟成を経たもの。甘み・旨み・香りのバランスがよく、飲みやすい味わい
・アネホ......1年〜3年未満の樽熟成を経たもの。オーク樽の香りとともに、やわらかな甘みと旨みを楽しむことができる
・エクストラアネホ......3年以上の樽熟成を経たもの。熟成期間が長いため、苦味や酸味がなくリッチな味わい
焼酎

焼酎は、芋、米、麦、そば、黒糖、栗などを原料とする蒸留酒です。日本の酒税法によって「焼酎乙類」「焼酎甲類」「混和焼酎」の3つに分類されています。
・焼酎乙類......「旧式焼酎」とも呼ばれる、古くからの製法で造られる焼酎のこと。芋、米、麦そば、黒糖などいろいろな食材を原料とし、その原料ならではの味わいを楽しめる。泡盛も焼酎乙類の一種
・焼酎甲類......「新式焼酎」とも呼ばれる、新しい製法で造られる焼酎のこと。サトウキビの糖蜜などを原料とし、クセのない味わいが特徴。酎ハイやサワーのベースに使われることが多い
・混和焼酎......「焼酎乙類」と「焼酎甲類」を混ぜ合わせたもの。両者の良いところを持ち合わせたお酒
熊本県(深野酒造本店)阿麓 Aroku 720ml
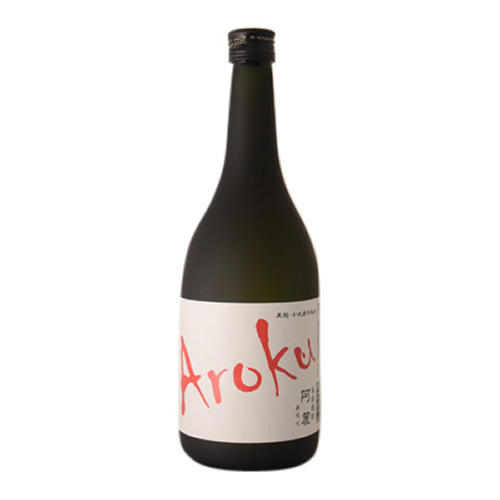
さっぱりとした麦や米に比べて、独特の風味がある芋焼酎。焼酎上級者にこそおすすめしたい一本がこちらです。原料の芋は、熊本の大津町でとれた「高系14号」を使用。深野酒造の代名詞である「かめ壷仕込み」で丁寧に作られており、深みのある味わいが楽しめます。
詳しく見る >
「混成酒」の定義と特徴
醸造酒や蒸留酒に、糖類や香料などを加えて作るお酒を「混成酒」と言います。代表的なのは、カクテルの原料となるリキュール。カシスやカルーアなどのリキュールをはじめ、お店で売られている缶チューハイやサワーも混成酒に分類されます。
混成酒の種類は?おすすめのお酒も!
リキュール

混成酒は原料や製造方法に明確な決まりはないため、種類はさまざま。リキュールは何をベースに造られているかによって、以下の4つに分類されています。
・ハーブ系リキュール......香草や薬草などを原料とするリキュール。カンパリ、ドライブンなどの銘柄が有名
・果実系リキュール......果物の果皮や果汁を原料とするリキュール。梅酒も果実系リキュールに分類される
・ナッツ、種子系リキュール......カカオ豆やナッツなど、果実の種子や豆類を原料とするリキュール
・その他......卵やヨーグルトなど、上記以外のリキュール。技術の進歩によって誕生した、比較的新しいリキュールが多い
ラングート ヴォーツェル ペーター 35゜

見た目も味もインパクト抜群!お酒の楽しみ方がグッと広がるハーブ系のリキュールです。商品名の「ヴオーツェル」は、ドイツ語で"根"の意味。その名の通り薬草や木の根から抽出された35種類ものエキスがブレンドされています。ブラックライトで照らすと、ラベルが光るという遊び心も。ドイツ農業協会のコンテストで3年連続金賞受賞の経歴をもつ、実力派のお酒です。
詳しく見る >
いろいろなお酒を味わってみよう
お酒の種類を知るうえでポイントとなるのは、「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」の3つ!この3つさえマスターすれば、お酒全体の構造を捉えやすくなりますよ。まずはいつも飲んでいるお酒は何に分類されているのか、原料や製造方法を調べてみることから始めるのがおすすめです。いろいろな種類をマスターしたら、普段は飲んだことがないお酒にもトライしてみてくださいね♪
※商品情報や販売状況は2022年04月25日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
スイーツ&グルメ 新着記事
-

CAKE LINK by HANKYU × 俳優 佐藤流司 2026年1月末までコラボ延長決定!!
ゆっきー
-

阪急のクリスマス~スイーツ~阪急うめだ本店のおすすめ
編集スタッフ
-

阪急のクリスマス~デリ~阪急うめだ本店のおすすめ
編集スタッフ
-

【12/20まで】「ケーキリンク」クリスマスケーキご予約まもなく終了
ゆっきー
-

クリスマス気分を先取り!~少し早めのPartyを楽しみませんか~
編集スタッフ
-

きかんしゃトーマス80周年・クリスマス映画公開記念ノベルティグッズ
ゆっきー
-

手土産に甘くないギフトを贈ろう!お菓子やおつまみ、調味料などおすすめ20選を紹介
贈りものナビ隊
-

「ケーキリンク」アンバサダーと共同開発 クリスマスドロップケーキ
ゆっきー
-

「ケーキリンク」クリスマスにおすすめキャラクターケーキ
ゆっきー
-

季節を味わう暮らし~かに編~阪急うめだ本店のおすすめをご紹介
編集スタッフ








