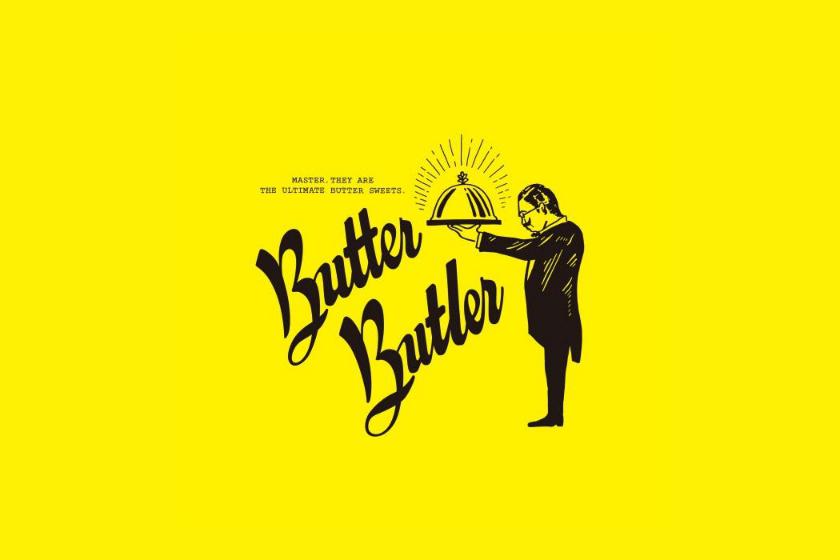ライフスタイル&ヘルス2025/4/15 更新
新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説
新盆とはお盆と何が違うのかご存じですか?新盆とはどんな行事なのか、何を準備したらよいのか、新盆飾りやお供えの仕方などポイントをわかりやすく解説します。また、新盆の法要に招かれた際のマナーについてもチェックしてくださいね。
新盆とは、何をする行事?

新盆とは、故人が亡くなって四十九日の忌明け(きあけ)後に初めて迎えるお盆のことです。四十九日以内にお盆がくる場合は、翌年に新盆をおこないます。
新盆は「にいぼん」「しんぼん」「あらぼん」など地域によって読み方はさまざまです。西日本では「初盆」と呼び、「はつぼん」「ういぼん」などと読みます。
新盆には故人の霊を家に迎えて供養をしたり、お墓参りをしたり、新盆の法要をおこなったりするのが一般的です。
通常のお盆との違い
お盆はご先祖様や故人の霊を家に迎え入れて供養をし、再びあの世へと送り出す行事です。ろうそくや提灯を灯してお供え物を供えたり、故人の家で供養をしたり、お墓参りに行ったりして過ごします。
古くから、故人の霊を初めて家に迎え入れる新盆は特に丁重におこなうべき行事と考えられてきました。通常のお盆とは違い、新盆には親戚や故人と親しかった人を招いて新盆法要をおこない、法要後には会食をするのが主流です。
新盆の時期はいつ?具体的な日程を解説

お盆の時期は地域によって違いがあるのをご存じでしょうか。全国的にお盆は8月におこなうケースが多いですが、東京をはじめ一部地域では7月、沖縄地方では9月にお盆を迎えます。新盆の時期も地域のお盆の時期に合わせるのが基本です。
2025年のお盆期間をご紹介します。
【2025年の地域別お盆期間】
・7月にお盆をおこなう地域......7月13日(日)~7月16日(水)
・8月にお盆をおこなう地域......8月13日(水)~8月16日(土)
・9月にお盆をおこなう地域......9月4日(木)~9月6日(土) ※一部地域は~9月7日(日)
お盆の時期が地域によって異なるのは明治時代の改暦がきっかけです。もともとお盆は旧暦の7月に営まれていた行事で、新暦では8月にあたります。
お盆の時期は、地域によって「新暦の7月」「新暦の8月」「旧暦の7月」と異なる暦を採用したため、3つに分かれました。
新盆とは忌明け後に初めて迎えるお盆を指す以外に、新暦のお盆を表わす場合もあります。
【行事の流れ】新盆の時期はいつ何をするの?

地域や宗派によっても違いがありますが、新盆の時期にはいつ何をおこなうのか、一般的な流れを解説します。
1. お盆初日(盆の入り)
精霊棚(しょうりょうだな)を飾り、お供え物を供え、故人の霊を迎える準備をします。仏壇も掃除し、ご先祖様や故人に思いをはせましょう。夕方には割り木で迎え火を焚き、白提灯を灯して故人の霊を迎えます。迎え火を焚けない場合は白提灯を灯せばOKです。
2. お盆の2~3日目
新盆法要をお寺または家でおこないます。僧侶に読経をしてもらい、参列者がお焼香をし、故人の霊を供養するのが目的です。新盆法要をおこなうお寺にお墓がある場合は、法要の前にお墓参りをします。新盆法要後は参列者や僧侶とともに会食をするのが一般的です。
3. お盆最終日(盆明け)
最終日は故人をあの世に送り出す日です。夕方に送り火を焚き、故人の霊が無事に旅立つのを見送ります。送り火は地域の伝統行事として根付いており、京都の大文字焼きや長崎の精霊流しなどが有名です。そのほか、各地で特色ある灯篭流しもおこなわれます。
【準備編】新盆法要とは?何をすればよいの?

故人が亡くなって初めてのお盆におこなう新盆法要。準備は新盆の1~2カ月前頃から始めたほうがよいでしょう。ここでは新盆法要に向けてやるべきことを解説します。
1. 新盆法要の手配
新盆法要に招待する人数を確認し、家またはお寺のどちらでおこなうかを決めます。お盆はお寺も忙しい時期であり、なるべく早めに日にちを相談するのがおすすめです。遠方から来る方や新盆法要後に会食することを踏まえ、日時を決めるとよいでしょう。
2. 会食の手配
新盆法要の日時が決まったら、会食の場所を決めます。レストランやセレモニーホール、ホテルなどを利用するのが一般的。料理は和食が選ばれることが多く、金額は3,000~10,000円が目安です。新盆法要後、会食場所までのアクセスによっては車の手配も必要になります。
3. 参列者への連絡
親戚や故人と親しかった方へ新盆法要と会食の案内状を送ります。「新盆法要と会食両方に出席」「新盆法要だけ出席」「欠席」なのか、また僧侶が会食に参加するかも確認しましょう。最終人数がわかり次第、お寺や会食場所へ連絡を入れます。
4. 返礼品の手配
新盆法要でお香典やお供え物などをいただいた方へは、感謝の気持ちを込めて返礼品を渡します。相場は1,500~5,000円程度。日持ちのするお菓子や食料品、日用品といった消え物がよく選ばれます。参列者の人数よりやや多めに用意すると安心です。
5. お布施の準備
新盆法要では僧侶へお礼としてお布施を渡します。相場は40,000円前後。奉書紙や白封筒に包み、表書きは濃墨で「お布施」「御礼」などと書きます。家でおこなう場合はお車代として別途5,000~10,000円、僧侶が会食を欠席する際は御膳料として5,000~10,000円程度を包みます。
【実践編】新盆飾り・お供えの準備の仕方

新盆を迎える際の飾り付けやお供えの仕方について解説します。
白提灯
白提灯はお盆に故人の霊が初めて家に戻ってくる際の目印です。通常のお盆では色や柄の入った提灯を飾りますが、新盆のみ白提灯を用います。お盆月の10日頃までに玄関や仏壇のある部屋などに飾り、お盆最終日には送り火で燃やすかお寺に納めるのが通例です。
精霊棚
お盆初日までに、故人の霊を迎え入れる精霊棚(盆棚)を用意します。テーブルや小机などで代用でき、仏壇の前か横に設置するのが通例です。仏壇から出した位牌を置き、ろうそくや線香、お供え物、精霊馬(しょうりょううま)などを供え、故人の霊をもてなします。
お供え物
お盆のお供え物は香・灯燭(とうしょく)・花・浄水・飮食(おんじき)の「五供(ごく)」が基本です。香はお線香、灯燭はろうそくを指し、花は香りが強すぎないものを選びます。食べ物は果物やお団子、お菓子、素麺や精進料理などが定番で、魚介類や肉類はNGです。
精霊馬
精霊馬とは故人の霊を送迎する乗り物のこと。きゅうりとなす、割りばしを使って馬と牛の人形を作り、精霊棚に飾ります。故人の霊がこの世に来るときは速く走れる馬に、あの世へ戻るときは牛に乗ってゆっくり戻ってほしいという意味が込められています。
【参列編】新盆法要に参列する際のマナーとは?

新盆法要や会食の案内が届いたら、速やかに出欠の返事をするのがマナーです。失礼のないように、新盆法要に出席・欠席する際のマナーについて確認しておきましょう。
香典
新盆法要に参列する際の香典は5,000~10,000円程度が相場です。会食がある場合は食事分として5,000~10,000円ほど上乗せするとよいでしょう。香典は不祝儀袋にお札の裏面が袋の表を向くように入れ、表書きは濃墨で「御仏前」「御供料(ごくうりょう)」などと書きます。
お供え物
新盆法要に招かれたら、香典とともに故人の霊をもてなすお供え物も持参します。線香やろうそく、供花、季節の果物や日持ちのするお菓子などが定番です。お供え物には「白黒の結び切り」のかけ紙を用い、表書きは「御供物(おくもつ)」と書きます。
服装
新盆法要へは喪服を着用して参列するのが基本です。数珠も忘れずに持参しましょう。「平服でお越しください」と案内がある場合でも、黒や紺、グレーなど落ち着いた色合いの服装が原則です。男性ならスーツ、女性はワンピースやアンサンブルなどがよいでしょう。
新盆法要に欠席する場合
新盆法要に参加できない場合は、お供え物や供花を送るか、供物料(供物の代わりに包む金銭)を現金書留で送ります。新盆前に施主に届くよう手配するのがマナーです。欠席の連絡をする際は、欠席のお詫びと故人を追悼する言葉を一筆添えると丁寧な印象を与えます。
新盆という節目を大切に
新盆は、遺族にとってもこの世に里帰りする故人の霊にとっても特別な節目です。一度きりの機会だからこそ、きちんと準備をして迎え、送り出したいもの。新盆の飾り付けや風習は地域や宗派によっても異なります。わからないことはお寺に相談するのがおすすめです。
※商品情報や販売状況は2025年04月15日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力
sara
-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説
秋山 ちとせ
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介
食ナビチャンネル
-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説
秋山 ちとせ
-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介
食ナビチャンネル
-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説
食ナビチャンネル
-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方
食ナビチャンネル