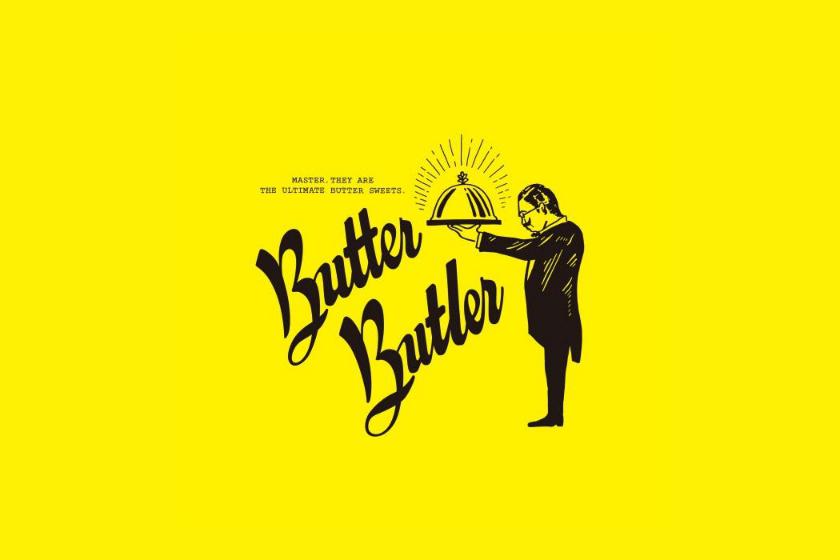ライフスタイル&ヘルス2024/1/6 更新
「処暑(しょしょ)」とは?2024年はいつ?意味や季節の特徴・食べ物を紹介
「処暑(しょしょ)」は、「立春」や「冬至」と同じ「二十四節気(にじゅうにしせっき)」のひとつ。暦のうえでは暑さが収まってくる時期であるとされています。この記事では、処暑とはいつの時期なのか、どんな季節なのかについて分かりやすく解説します。
2024年(令和6年)の「処暑」はいつ?

処暑(しょしょ)は、中国を起源とする暦(こよみ)「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつです。
処暑の始まりは毎年8月23日ごろ、終わりは9月6日ごろですが、毎年同じ日付ではありません。2024年と2025年の処暑の期間は、以下のとおりです。
・2024年の処暑:8月22日〜9月6日
・2025年の処暑:8月23日〜9月6日
処暑の前には、暦上の「秋」の始まりである「立秋(りっしゅう)」があります。そのあとにくる季節は「白露(はくろ)」。白露は「草木に露がつき、白く光って見えるころ」であり、少しずつ秋の気配が感じられるようになる季節であるとされています。
処暑の日付はどうやって決まる?
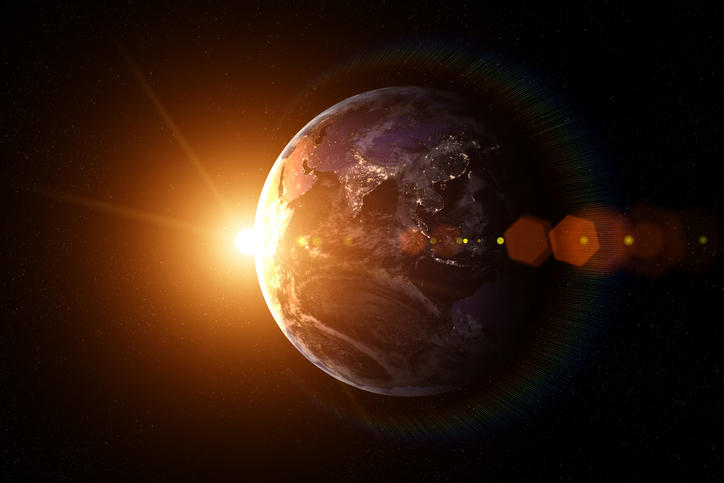
二十四節気のひとつである処暑の日付は毎年同じではありません。二十四節気は、1年を春・夏・秋・冬の4つの季節に分け、それぞれの季節をさらに6つに分けた24の季節です。日付はその年の太陽の動きをもとに決められているため、毎年異なります。
そもそも処暑とは?どんな時期?

処暑はだんだんと暑さが収まってくるころとされています。多くの学校では夏休みが終了し、新学期が始まる時期でもあります。
実際には残暑厳しい時期とはいえ、暦上はすでに秋に入っている処暑。朝晩と日中との寒暖差が大きくなってくる時期でもあるため、体調管理には注意が必要です。
夏の終わりを感じる処暑の季節の風物詩

処暑を迎えると、各地でさまざまな行事がおこなわれます。
近畿地方でおこなわれるのは、お地蔵さんにまつわる「地蔵盆」と呼ばれる行事。地域によって内容は異なりますが、町内のお地蔵さんをきれいにしたり提灯を飾ったり、縁日や盆踊りが開催されたりする地域もあります。
そのほか、山梨県の「吉田の火祭り」や、富山県の「おわら風の盆」なども処暑の時期におこなわれるお祭りです。
処暑の食べ物・過ごし方

処暑のころに旬を迎える野菜や果物には、ぶどうやいちじく、さつまいもなどがあります。また処暑を迎えるころに出回りはじめる魚といえば、秋の味覚の代表格「秋刀魚(さんま)」。まだはしりの時期ではありますが、だんだんと脂ものっておいしくなってくるころです。
暑さが残る時期とはいえ、季節の移り変わりを感じるようになる処暑。旬の食材をおいしく味わいながら、ゆっくりと夏の疲れを癒すべき時期なのかもしれませんね。
暦上は秋でもまだまだ暑い「処暑」
二十四節気のひとつ「処暑」は、毎年8月23日ごろ〜9月6日ごろ。毎年同じではないのは、その年の太陽の動きをもとにして決められているからです。8月下旬〜9月上旬はまだ暑さが残る時期ですが、出回り始める秋の味覚を味わいつつ、夏の疲れをリセットしましょう。
「夏みやげ特集」を見る
※商品情報や販売状況は2024年01月06日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力
sara
-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説
秋山 ちとせ
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介
食ナビチャンネル
-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説
秋山 ちとせ
-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介
食ナビチャンネル
-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説
食ナビチャンネル
-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方
食ナビチャンネル