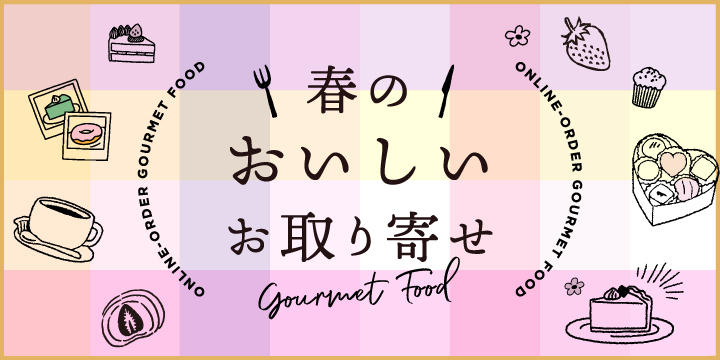ライフスタイル&ヘルス2025/2/13 更新
啓蟄の食べ物とは?意味や由来、風物詩や季節の草花などを解説
みなさんは「啓蟄」とは何かご存じでしょうか?「名前は聞いたことがあるけれど、意味や由来はわからない」「具体的に何のこと?」と疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、啓蟄とは何か、意味や由来、それにまつわる旬の食べ物・草花などを紹介します。
啓蟄(けいちつ)とは

「啓蟄(けいちつ)」とは、季節を四季よりもさらに細かく分けたものである「二十四節気」のひとつ。春が来る直前の、冬眠していた生き物たちが目覚める3月上旬ごろ〜3月中旬ごろの時期を指します。
啓蟄の「啓」は開く・開放、「蟄」は虫の冬ごもり(土の中に隠れて閉じこもる)のことを意味し、春の訪れに向けて虫たちが土から出てくる様子を表現しています。
啓蟄の日付はいつ?
そもそも二十四節気とは
そもそも「二十四節気(にじゅうしせっき)」とは、太陽の当たる量に合わせて設定された暦のこと。1年間を春夏秋冬の4つに分け、さらにそれらを6つに分けて24等分(節気や中気)にして、それぞれの時期に名前を付けています。
啓蟄のほかには、立春、春分、夏至、大暑、立秋なども二十四節気の一種。それぞれ、その年によって日付が異なり、1日ほど前後することがあります。
啓蟄の期間・日付
啓蟄の具体的な日程は毎年若干の変動があり、例年3月5日〜3月19日ごろです。また、ひと言で「啓蟄」といっても、啓蟄から春分までの一定期間を指す場合と、単に「啓蟄に入る日」を指す場合があります。
2024年〜2028年までの「啓蟄に入る日」の日付・曜日は、下記のようになっています。
・2024年の啓蟄の日 ...... 3月5日火曜日
・2025年の啓蟄の日 ...... 3月5日水曜日
・2026年の啓蟄の日 ...... 3月5日木曜日
・2027年の啓蟄の日 ...... 3月5日土曜日
・2028年の啓蟄の日 ...... 3月5日日曜日
啓蟄に食べるもの
季節が冬から春に移り変わり、徐々に生き物が顔を出す啓蟄。気温も上がり、旬の食べ物が豊富な時期です。ここでは、啓蟄の時期に旬を迎える食べ物をいくつか紹介します。山菜やたけのこ、にしんなど、春らしさを感じる食材がたくさんあるので、ぜひ料理に役立ててみてくださいね。
山菜

啓蟄に旬を迎えるのは、ほろ苦い風味の「ふきのとう」やシダ植物の一種で粘り気の強い「わらび」、独特の所感がある「ぜんまい」などの山菜です。まだ芽を出したばかりの若々しさを感じられ、ほんのり苦味を感じられるものが多いのが特徴。
アクの強いものは、重曹や熱湯を使ってアク抜きをしてから調理すると、美味しく食べることができますよ。
たけのこ

たけのこも3月〜5月ごろ、啓蟄の時期に旬を迎える食べ物のひとつです。クセの少ない淡白な味わいと食感の豊かさが魅力的。しっかりとした歯ごたえがあり、煮物から焼き物、揚げ物までさまざまな料理に使いやすいのも特徴です。
たけのこを入れた炊き込みご飯や、若竹煮、丸ごと焼いたものや田楽まで、レシピのレパートリーも豊富ですよ♪
さより

3月〜5月ごろに旬を迎える魚・さよりも、啓蟄に食べたい高級食材です。引き締まった身と、透き通るような透明感が美しい逸品。クセが少なく、上品かつ淡白な味わいを堪能できます。
いち押しの食べ方は新鮮な状態で、生のまま食べること。寿司ネタとしていただくのはもちろん、刺身や天ぷら、フライなど、いろいろな食べ方で楽しむことができます。
にしん

数の子の親魚として知られるにしんも、啓蟄の時期に旬を迎えます。別名「春告魚(はるつげうお)」ともいわれ、俳句で春の季語としても親しまれていますよ。脂がたっぷりのった味わいと、ほろほろと崩れる身の食感が楽しめ、ほど良い渋みを感じられる魚です。
料理は定番の塩焼きや蒲焼きをはじめ、「にしんそば」や煮付け、マリネまで幅広く活用できます。
はまぐり

2月〜4月ごろに旬を迎えるはまぐりも、啓蟄におすすめの食べ物。ふっくらとやわらかな身と、口いっぱいに広がるうま味が魅力の食材です。ひな祭りに食べると良縁を招くとされており、縁起ものとしての役割もあります。
バターや醤油で味付けして網で焼いたり、ゆでて和えものにしたりするのが一般的。味噌汁に入れらり、お吸い物にしたりするのもおすすめですよ。
啓蟄の風物詩・花

菰(こも)はずし
啓蟄の風物詩のひとつとして「菰(こも)はずし」というものがあります。これは冬の間に、害虫から松の木を守るために付けられた菰を、温かくなる春を前に外すという行事です。
菰とは藁(わら)で作るむしろのこと。虫が動き出す啓蟄の時期に外すことで、なかに入っている害虫を駆除する目的があります。
虫出しの雷
啓蟄の時季に鳴る雷のことを「虫出しの雷」と呼ぶことも。これは春の雷である「春雷(しゅんらい)」の音に驚いた虫たちが、冬眠中の土・穴のなかから飛び出してくる様子を表現したものとされます。俳句でも雷を表現する春の季語として、たびたび用いられる言葉です。
春雷は夏の夕立とは異なりすぐに鳴りやむことが多く、生き物たちにとっても春を告げる合図となっているかもしれませんね。
季節の花「桃」
啓蟄の時期に旬を迎える花として代表的なものが「桃」です。ちょうどこの時期に、桃のつぼみが開き花が咲きはじめるのが特徴。鮮やかなピンク色を見ると、春の訪れを感じさせますね。
二十四節気のひとつを、さらに3つに分けた「七十二候(しちじゅうにこう)」でも、3月10日〜3月14日ごろは「桃始笑(ももはじめてさく)」という名前が付けられています。昔の人たちは花が咲くことを「笑う」と表現したのだとか。
季節の花「かたばみ」
啓蟄の時期の草花として親しまれているもののひとつ「かたばみ」も春らしい植物です。クローバーのようなハート型の3枚の葉から、小さな黄色い花をつけるのが特徴。品種によっては白やピンク、紫などカラフルでかわいらしい色を楽しめます。
夜になると葉を閉じるため、眠っているように見えるのも特徴的。クローバーとは似て非なるもので、繁殖力が高く力強さのある植物です。
啓蟄におすすめのレシピ5選
1. 基本のたけのこの若竹煮

啓蟄の時期に旬を迎えるたけのこと、生わかめを贅沢に使用する若竹煮は淡泊な味わい。だしをよく効かせるので、上品で奥深いひと品に仕上がります。
春らしさを感じるやさしい味わいは、たけのこの素朴な風味をより引き立てます。おかずにもうひと品ほしいときに最適!調理中は、わかめの風味を損なわないように煮込み過ぎにご注意ください。
レシピはこちら|macaron
2. うどのきんぴら

印象的な香りが特徴のうどを使う、副菜にうってつけのきんぴら。一味唐辛子のアクセントを効かせて、ピリッと刺激的なテイストに仕上げます。
おつまみにもうれしいひと品。きんぴら特有のシャキシャキとした食感を出すには、水分を飛ばすことが重要です。強火で短時間加熱することにより、一気に水分が抜けて歯ごたえが良くなります。
レシピはこちら|macaroni
3. ぜんまいナムル

春の山菜であるぜんまいを使用する韓国風味のナムルは、ほのかな苦味を楽しめるひと品。しっかりとした歯ごたえと、さっぱりとした後味がクセになります。
ぜんまい特有の香りが気になるときは、熱湯でさっとゆでると調味料となじみやすくなります。炒めるときに水分をしっかり飛ばすのが、おいしく作るコツです。
レシピはこちら|macaroni
4. 山菜散らしおこわ

タラの芽やぜんまいの水煮、うどなど、春の山菜をいくつか入れて作るおこわのレシピ。ほんのり青さと苦味を感じる山菜は、おこわにするとおいしさがさらに増します。もち米のもちっと感と、山菜のシャキシャキ感が合わさり飽きのこない食感に。
調理するときは、味をよく染み込ませるため、蒸す前にだしをしっかりと煮含ませるのがポイント。少し手間はかかりますが、調理工程も含めて春らしさを感じるレシピです。
レシピはこちら|macaroni
5. にしんの塩焼き

こちらのレシピでは、にしんの内臓を取らずに丸ごと焼きます。ふっくらと焼き上がった塩焼きのにしんは、シンプルながらおいしいですよ。内臓を取り出す場合は、白子や卵を別の料理に仕立てるのがおすすめ。
にしんの独特の臭みが気になる方は、塩水で洗うことで取り除くことができます。また焼き上がったあと、1分ほどグリルのなかに置いておくことで、なかまでしっかり熱が通りますよ。
レシピはこちら|macaroni
啓蟄の食べ物・草花から春の訪れを感じよう!
啓蟄とは、3月5日〜3月19日ごろにかけての時期を指す二十四節気のひとつ。冬眠していた生き物たちが徐々に目を覚ます、春の訪れを感じさせる時期です。この季節にしか楽しめない旬の食べ物・風物詩・草花などがたくさんあるので、ぜひ目や舌で味わってみてくださいね。
「春のおいしいお取り寄せ」特集はこちら
※商品情報や販売状況は2025年02月13日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力
sara
-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説
秋山 ちとせ
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介
食ナビチャンネル
-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説
秋山 ちとせ
-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介
食ナビチャンネル
-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説
食ナビチャンネル
-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方
食ナビチャンネル