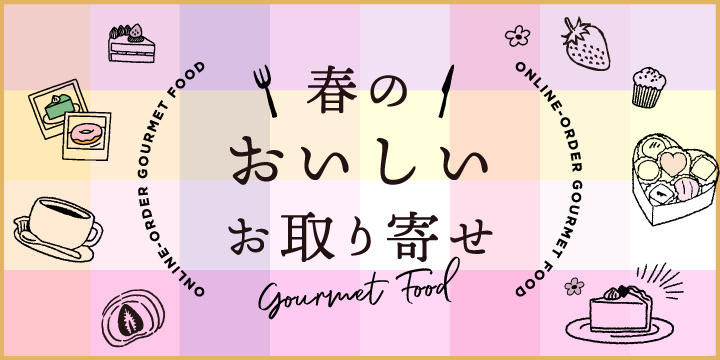ライフスタイル&ヘルス2025/2/16 更新
穀雨(こくう)の意味・由来。ほかの呼び方やおこなわれる行事を解説
みなさんは「穀雨」という言葉をご存知でしょうか?「手紙や俳句などで目にしたことはあるけれど、実際の意味や由来などはわからない......」という人も多いかと思います。そこでこの記事では、穀雨の意味や由来を簡単に解説。その時季に旬を迎える植物・食べ物なども紹介します。
「穀雨(こくう)」の意味・由来

「穀雨(こくう)」は、二十四節気のひとつで「恵みの雨がたっぷりと降り注ぐ頃」です。二十四節気は、四季をさらにむっつに分けた暦で、現代でも立春・春分・冬至などが親しまれています。穀雨はそのうちの6番目の節気で、現在の暦では4月下旬〜5月初旬ごろとなり、2024年は4月19日〜5月5日が穀雨です。
穀雨は「雨生百穀(うりゅうひゃっこく)」より由来すると言われています。この言葉には"春雨が百穀を生む"という意味があり、地上にある食物に水分と栄養がため込まれる時期とされるため、昔から穀雨を目安に種まきや田植えがおこなわれてきました。
穀雨の終わりに訪れる縁起の良い日「八十八夜」

穀雨の終わりに訪れる「八十八夜(はちじゅうはちや)」。茶摘みの歌などで知られるこの日は、実は農作業に縁起の良い日とされています。理由は、末広がりの"八"が重なることや「八」「十」「八」を組み合わせると「米」になるため。
さらに、茶葉の産地では八十八夜に茶葉の初摘みをおこなうとされ、この日に採れた茶葉を使った"一番茶"を飲むと、無病息災で過ごせると言い伝えられてきました。たっぷりと栄養素を含んだ新芽の一番茶は、旨味や甘味のある味わいが楽しめますよ。
穀雨の別の読み方

穀雨の時期に降る、春の恵みの雨には、「甘雨(かんう)」「春霖(しゅんりん)」「木の芽雨(このめあめ)」「瑞雨(ずいう)」などの別名もあります。甘雨はやさしく降るような雨を、春霖は長く降る雨を指し、木の芽雨と瑞雨は木の芽や穀物の成長を助ける・育てるという意味が込められていますよ。
穀雨の植物・食べもの

穀雨に旬を迎える植物には、美しく垂れ咲く藤の花が挙げられます。圧倒的な存在感と品のある紫色が特徴で、甘く爽やかな香りが楽しめますよ。
また、この時期によく食べられるものは、アスパラガス・筍(たけのこ)・さやえんどうといった春野菜です。サラダや炒めもの、天ぷらなど、さまざまに調理できるので、ぜひいろんな食べ方に挑戦してみてくださいね。
穀雨は恵みの春雨がたっぷり降る頃
手紙の文頭や俳句などに用いられる「穀雨」は、恵みの雨がたっぷりと降り注ぐ、4月下旬〜5月初旬の節気です。この時期には藤の花が咲き誇り、多くの春食材が旬を迎えるので、ぜひ季節の風景や味を楽しんでくださいね。
阪急の「春のおいしいお取り寄せ」特集
「春のおいしいお取り寄せ」特集はこちら
※商品情報や販売状況は2025年02月16日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介
贈りものナビ隊
-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選
贈りものナビ隊
-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで
贈りものナビ隊
-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介
贈りものナビ隊
-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説
食ナビチャンネル
-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも
贈りものナビ隊
-

父の日はいつどこではじまった?起源や由来&おすすめギフト5選
食ナビチャンネル
-

新盆とは。いつ何をどのようにすればいいの?ポイントをわかりやすく解説
食ナビチャンネル
-

新盆のお供え物|選び方・相場・渡し方・贈り方のマナーを徹底解説!
食ナビチャンネル
-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力
sara