
ライフスタイル&ヘルス2024/5/20 更新
新茶の季節「八十八夜」とは?何をする日?日付や由来・豆知識を紹介
八十八夜(はちじゅうはちや)という言葉は茶摘みの歌でもおなじみです。とはいえ、聞いたことはあってもよくは知らないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、八十八夜の由来や日付、新茶との関係について紹介します。お取り寄せできる新茶やお茶商品の情報も要チェックですよ。
八十八夜とは?歴史や由来を紹介

八十八夜とは雑節(ざっせつ)のひとつで、立春から数えて88日目にあたる日のことをいいます。八十八夜の日付は毎年異なりますが、大きなずれはなく、時期は5月初旬とほぼ一定です。
ちょうど春から初夏へと移り変わり、気候も安定する頃。古来より、農作業を始める目安の日とされてきました。
雑節は二十四節気とは違うの?
二十四節気とは中国伝来の暦で、一年を二十四の節気に区分し、「立春」「立夏」など季節の目安となる名称を付けたものです。
一方、雑節とは二十四節気の補助的な節気として、日本の気候風土に合わせて作られたもの。「八十八夜」をはじめ、「入梅(にゅうばい)」「土用(どよう)」「節分」などがあり、季節の移り変わりをより明確に表しています。
八十八夜はいつ?具体的な日付を紹介

八十八夜の日付は、立春の日付から起算して決められます。立春の日付は毎年異なるため、八十八夜の日付も年により違いがあります。2024年から2027年にかけての八十八夜の日付は以下の通りです。
<2024~2027年までの八十八夜の日付>
2024年...... 5月1日(水)
2025年...... 5月1日(木)
2026年...... 5月2日(土)
2027年...... 5月2日(日)
八十八夜は何をする日?

新緑がまぶしい八十八夜の頃は、遅霜(おそじも)の心配もなく、農家にとっては本格的な農作業を始める目安の日です。野菜・穀物の種まきや田植えの準備などがおこなわれます。
お茶農家にとって、八十八夜は新芽の茶摘みをおこなう特別な日。「夏も近づく八十八夜」という歌詞で始まる茶摘みの歌は、まさに八十八夜の茶摘みの様子を歌ったものです。
南北に長い日本では産地やお茶の種類によって新茶の収穫時期は異なり、八十八夜を含む4~5月頃が収穫の最盛期。その年の新芽で作られたお茶は「新茶」または「一番茶」として市場に出回ります。
八十八夜の特別な食べ物や行事食
八十八夜には、この日恒例の食べ物や行事食などは特にありません。とはいえ、やはりこの時期ならではのフレッシュな新茶はぜひとも味わいたいもの。最近では新茶を使ったスイーツも和洋問わず登場しており、おいしい新茶と一緒に楽しむのもおすすめです。
八十八夜の時期に収穫される「新茶」の魅力とは?

新芽ならではのフレッシュで爽やかな香りは、新茶ならではです。味わいは苦味や渋味が少なく、旨味や甘味が濃いのが特徴。香りや味わいから、新芽特有の若々しいエネルギーが感じられます。
また、初物(はつもの)である新茶は、古くから不老長寿の縁起物として珍重されてきました。新芽には冬の時期に蓄えられた栄養素や旨味成分が豊富に含まれ、「八十八夜に摘まれたお茶を飲むと長生きできる」「新茶を飲むと病気にならない」ともいわれているそうです。
阪急百貨店おすすめ!新茶を扱う有名ブランド2選を紹介
阪急百貨店でお取り寄せ可能な人気のお茶ブランド「茶匠 森半」「一保堂茶舗(いっぽうどうちゃほ)」から、新茶や人気のお茶商品を紹介します。
1. 伝統と革新を兼ね備えた宇治茶の匠「茶匠 森半」
京都の茶どころとして名高い、宇治の伝統を守り続ける「茶匠 森半」。1836年の創業以来、高い品質にこだわったお茶づくりに取り組んでいます。伝統ある商品を大切にしながらも、新商品の開発や新技術の導入にも積極的にチャレンジ。日本茶の楽しみを広げています。
「茶匠 森半」煎茶 初摘み
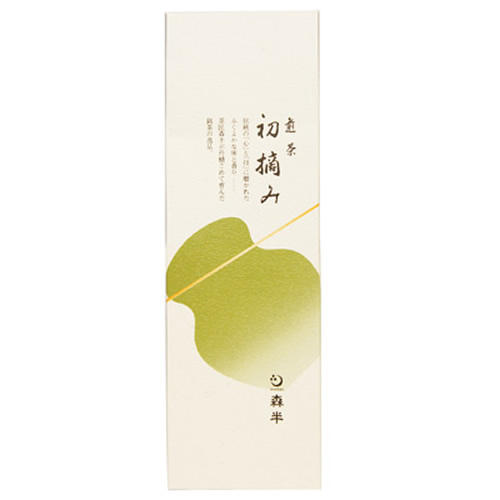
この時期にしか味わえない、初摘みの茶葉を使用した上級煎茶です。香りはすっきりとして清涼感があり、旨味や甘味がギュッと凝縮されたような味わいが特徴的。いつもよりゆったりとお茶を楽しみ、リラックスしたひとときを過ごしてみませんか。
詳しく見る
「茶匠 森半」煎茶 森半八十八夜
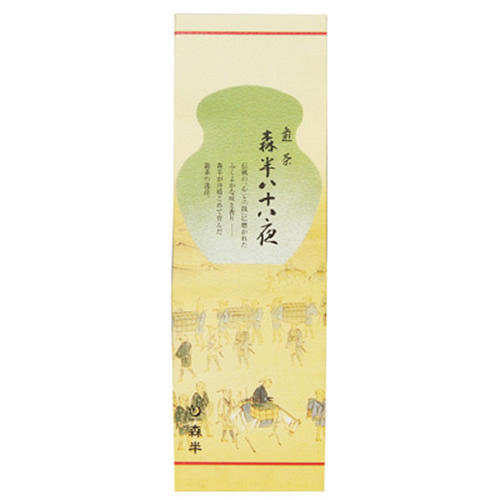
八十八夜と名付けられた煎茶は、森半の看板商品。日本屈指の茶師が厳選した良質な茶葉を使用しています。爽やかな香りや口の中に広がるふくよかな旨味が魅力的。八十八夜の時期に収穫された茶葉ならではの、いきいきとした風味をお楽しみください。
詳しく見る
2. 老舗の品格ある味わいを楽しむ「一保堂茶舗」
創業1717年、京都に本店を構える一保堂茶舗。屋号には「茶、一つを保つ」という意味が込められており、真摯に日本茶と向き合い続けています。普段使いできるものから贈答用まで、さまざまなシーンに寄り添う日本茶が充実。新茶は6月上旬までの期間限定で販売されています。
「一保堂茶舗」ドリップティーバッグ煎茶

ドリップティーバッグをカップにセットし、熱湯を注いで1分待てばOK。急須でいれたような豊かな煎茶の風味を手軽に楽しめます。香りがよく、旨味と渋味のバランスに優れ、飲み飽きることがありません。普段使いやちょっとした手土産にもぴったりです。
詳しく見る
「一保堂茶舗」玉露鶴齢・煎茶薫風 詰合せ

若芽を使用した香り爽やかな煎茶「薫風」と、コクのある旨味が持ち味の玉露「鶴齢」の詰め合わせ。使いやすい少量タイプの缶入りです。上質なお茶の飲み比べを楽しんでみてはいかがでしょう。ご自宅用としてはもちろん、ギフト使いにもおすすめです。
詳しく見る
八十八夜は新茶を楽しもう!
日本ならではの風習が息づいている八十八夜。農作業を始める大事な節目の日であり、新茶とのかかわりが深い日です。初摘みの茶葉を使った新茶が出回るのは、一年のなかでもほんの一時。ぜひこの時期に、新緑を思わせるような爽やかな新茶をお楽しみくださいね。
※商品情報や販売状況は2024年05月20日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

節分とはどんな行事?由来や歴史、食べ物をわかりやすく解説
食ナビチャンネル
-

2026年の大寒(だいかん)はいつ?冬至・小寒との違いや風習、食べ物も紹介
食ナビチャンネル
-

ホワイトデーにチョコを贈ってもいい?お返しのお菓子に込められた意味とは
食ナビチャンネル
-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力
sara
-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説
秋山 ちとせ
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介
食ナビチャンネル
-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説
秋山 ちとせ








