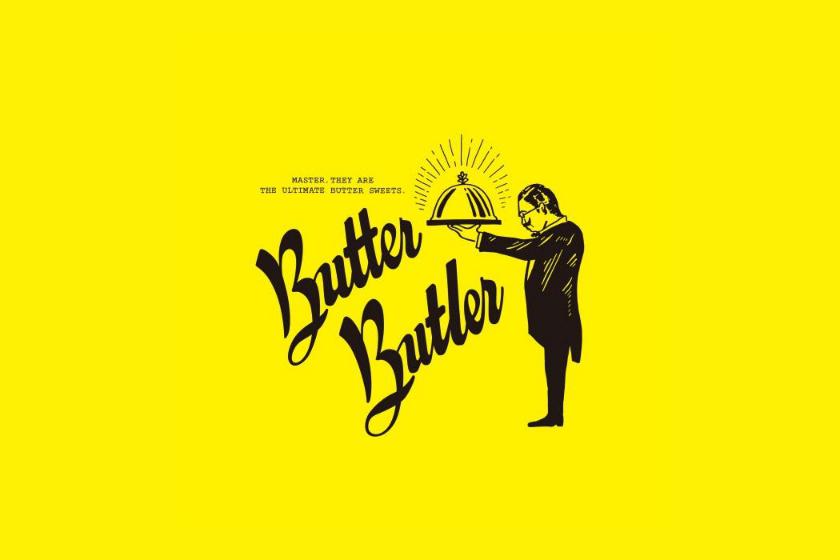ライフスタイル&ヘルス2024/7/23 更新
節分に豆まきするのはなぜ?由来や正しいやり方、そのほかの風習についても解説
節分は日本の伝統行事。特に子どもがいる家庭では豆まきをすることも多いのではないでしょうか。今や当たり前になっている節分の豆まきですが、その由来や意味をご存じですか?本記事では節分に豆まきをする理由や由来をはじめ、決まり事や正しい豆まきの仕方を解説します!豆まきの歴史を知って、節分をより楽しむ準備をしましょう♪
節分の「豆まき」の由来・理由は?正式なやり方もチェック

2月3日は節分です。子どものころから当たり前に豆まきをしている人も多いはず。鬼の仮面を被った人に向かって投げたり、玄関に向かって投げたり......。年中行事として何気なくやっている節分の豆まきですが、その由来や豆を投げる理由、正しい豆まきの仕方などをご存じですか?
本記事では節分の豆まきの由来や理由、正式なやり方を解説します。豆まき以外の節分の風習も紹介しますので、この機会にぜひ知っておきましょう。
節分とは
節分は、季節の変わり目のこと。具体的には立春・立夏・立秋・立冬の前日を指します。「節分は2月3日のみ」という印象がありますが、もともとは春夏秋冬、すべての季節の節目をさす言葉です。
そのなかでも、旧暦で新年のはじまりを表す春がもっとも重要とされ、現在では2月3日の節分が一般的になりました。
節分の「豆まき」の風習はいつから?歴史と由来

今や節分に当たり前におこなわれる豆まき。季節の節目にはおめでたいイメージがありますが、昔から悪いものが家に入りやすい時期と考えられてきました。それらを退治するためにおこなうようになったのが豆まきです。
はじまりは古代中国でおこなわれていた「追儺(ついな)」という風習。その文化が飛鳥時代に日本に伝わり、宮中行事としておこなわれるようになりました。
ただ、豆まきがおこなわれるようになった明確な時期は不明です。しかし、江戸時代には節分の豆まきが完全に定着したといわれています。このことから、豆まきにはかなり長い歴史があることがわかりますね。
鬼に豆をまくのはどうして?
仏教では、鬼は煩悩を表します。節分の鬼は赤か青のイメージがありますが、実はほかにも緑・黒・黄の鬼がいるのをご存じですか?赤は欲望、青は怒り、緑はやる気が出ない、黒は疑い、黄色は甘えなどの意味があり、それぞれが違う煩悩の種類を表しているのです。
この5つのなかから、自分が打ち勝ちたい煩悩を選び、それを表す鬼に豆をぶつけるといい......といういわれがあります。鬼に豆をまくことで煩悩を追い払い、気持ち良く新しい季節を迎える意味があるのですね。
節分の豆まきに「大豆」を使うのはなぜか

日本では、古くから米、麦、ひえ、あわ、大豆には"穀霊"と呼ばれる精霊が宿っていると考えられていました。そのなかでも大豆はもっとも粒が大きく、ほかより多くの精霊が宿るとされています。そのため、鬼の退治に最適とされ、豆まきによく使われているのです。
また、「魔の目に豆をぶつけ、魔を滅する」の語呂合わせとしての意味もあります。豆には縁起の良い意味がたくさんあるのですね。
豆まきに「落花生」を使う地域も
北海道や東北をはじめ、新潟や長野など比較的雪が多く降る地域では大豆より落花生を使用するのが一般的です。雪がたくさん積もる地域では、大豆よりも大きい落花生のほうが拾いやすく、地面に落ちても衛生的だからといわれています。
豆まきの決まり事
炒り豆を使う
豆まきには炒った大豆を使うのが一般的。豆を「炒る」と悪いものを「射る」をかけており、縁起が良いためです。また、生の豆を使って万が一拾い忘れたとき、芽が出ることがあります。これは「邪気が芽を出す」ことを意味し、縁起が悪いこととされているので注意しましょう。
豆まきをする時間帯
一般的に、豆まきは夜におこなうほうがいいとされています。豆をまく対象である鬼が夜にくるためです。心の煩悩を追い払い、新しい季節をすっきりした状態で迎えるためにも、家族全員がそろう夜に豆まきをしましょう。
食べる豆の数
豆まきをしたあと、自分の年+1つぶんの豆を食べることを知っている人は多いでしょう。これは「年取り豆」と呼ばれ、1年の厄除けを願う意味がある風習です。ただし、地域によっては「数え年として1つ多く食べる」「数え年と新年のぶんを加えて2つ多く食べる」「年の数だけ食べる」など、内容に違いがあることもあります。
豆まきの正式なやり方
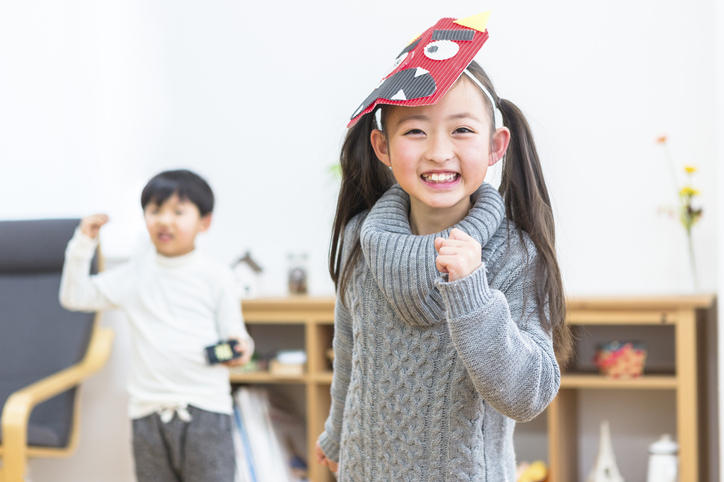
手順1. 夜までに福豆を準備する
鬼がくる夜までに福豆と呼ばれる炒った大豆を用意します。豆まきをする夜までは桝(ます)や三方(さんぽう)という神様にお供えものをする器に入れ、神棚に供えておくのが一般的です。
手順2. 奥の部屋から豆をまいていく
夜に家族全員がそろったら、玄関から遠い部屋から豆をまきはじめます。これには家の奥の部屋から順に鬼(煩悩)を追い出すという意味が込められています。鬼を追い出し切るために、最後は玄関までまきましょう。豆をまく順番や方角は地方ごとに異なるため、確認しておくといいですね。
手順3. 家の玄関や窓を開けて「鬼は外!」と豆をまく
まず鬼を追い出すために、玄関や窓に向かって「鬼は外!」と豆をまきます。大きな声や音は魔除けになるため、勢いよくおこなうのがポイントです。
手順4. 戸や窓を閉めて「福は内!」と部屋の中に豆をまく
次に、鬼が戻らないようにすぐ戸や窓を閉め、「福は内!」と部屋の中に豆をまきます。ここでも戸や窓を閉める勢いが大切です。「ピシャリ!」と音を立てて閉めましょう。
手順5. 豆を食べる
豆まきが終わったら、年の数よりひとつ多く豆を食べます。子どものうちは年の数だけ豆を食べることもむずかしくありませんが、数が増えて食べきれなくなってきたら福茶というお茶にしていただくといいですよ。
ほかにも節分にはこんな風習も!

恵方巻きを食べる
その年の恵方を向いて太巻き寿司を食べる節分の風習は有名です。さまざまな決まり事がありますが、丸ごと1本をひと言も話さずに食べきることがほとんど。恵方巻きを切らずに丸ごと食べることには「大事なご縁を切らないために」という意味があり、無言で食べることには「話しながら食べると福が逃げるから」といういわれがあります。
いわしを飾る
近畿地方を中心に、いわしの頭を焼き、柊(ひいらぎ)の枝を刺した「柊いわし」を家の玄関や窓際に飾る風習もあります。家の中に入ろうとする鬼を、いわしの強いにおいで驚かせ、柊の枝で鬼を刺すという意味を持つ儀式です。地域によってはいわしの代わりににおいが強いねぎを使ったり、柊の代わりに串を使ったり場合もありますよ。
けんちん汁で身体をあたためる
関東地方では節分にけんちん汁を食べる風習も。ごぼうやにんじんなどの根菜、こんにゃくなどのほかに、豆まきに使った大豆を入れる地域もありますよ。節分は2月の寒い時期におこなわれるため、冷えた身体を温めるためだとされています。
こんにゃくで悪いものを外に出す
食物繊維が多く含まれるこんにゃく。食べることで「身体の毒素を出す」と考えられていて、「胃のほうき」ともいわれる食べ物です。節分などの季節の節目に身体の悪いものを外に出して体内をきれいにするために、現在でも四国地方などでこんにゃくが食べられています。
余った福豆で作るおすすめレシピ3選
1. 毎日の食事で使える「福豆味噌」

福豆を甘辛テイストの味噌に絡めて作る、福豆味噌。味噌汁やサバの味噌煮など、さまざまな料理に使えるため消費しやすいレシピです。味噌らしい心温まる香りが魅力的。福豆は焦げやすいので弱火でじっくり炒めるのがポイントです。煮詰めるときは固くなり過ぎないように、適宜時間を調整しましょう!
レシピはこちら|macaroni
2. ザクザク食感「鶏むね肉のザクザク福豆フライ」

余った福豆を砕いてパン粉のように使用することで、ザクザク食感を生み出せます。鶏むね肉をカラっと揚げて、食べ応えのあるひと品に。福豆はクセがなくすっきりとしたテイストなので、衣に使用すると肉のうま味を引き立てます。食卓の主役を張れる、ボリューム満点なレシピです!
レシピはこちら|macaroni
3. とろける甘さ「ざくざくチョコバー」

福豆にミルクチョコレートを掛け合わせて、まったくテイストの違う新感覚スイーツを楽しめるレシピ。まろやかなチョコの甘さに、福豆特有のカリッと軽い食感が合わさりほかにはない風味に仕上がります。ドライフルーツやナッツなどで、おしゃれに飾り付けすると写真映えもしますよ!
レシピはこちら|macaroni
豆まきの由来や正しいやり方を知って節分を楽しもう!
節分になると当たり前にしていた豆まき。しかし歴史や決まり事、正しいやり方などを詳しく知らない人は意外と多いのではないでしょうか。節分には豆まき以外の伝統的風習がたくさんあります。ぜひいろいろと知って、次の節分を楽しんでみてくださいね。
恵方巻のご予約はこちら
※商品情報や販売状況は2024年07月23日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力
sara
-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説
秋山 ちとせ
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介
食ナビチャンネル
-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説
秋山 ちとせ
-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介
食ナビチャンネル
-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説
食ナビチャンネル
-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方
食ナビチャンネル