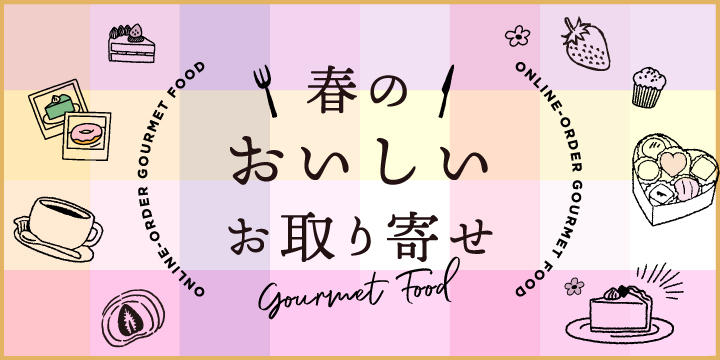ライフスタイル&ヘルス2025/2/8 更新
春分の日は何をする日?日本の歴史や仏教との関わりや、食べるといいものを解説
毎年3月20日頃に訪れる、春分の日。一年のなかで昼と夜の長さが同じになる日として知られていますが、毎年日にちに変動がある理由や、その背景を知る人は少ないのではないでしょうか。この記事では、春分の日にまつわるさまざまな疑問や豆知識を解説していきます。
春分の日とは?どんな意味を持つのかチェック

毎年同じ日ではない祝日「春分の日」。「今年の春分の日はいつ?」なんて会話をされる方も多いのではないでしょうか。
この記事では春分の日の由来にはじまり、祝日になった理由や具体的に何をするのかなどを解説。なぜ年ごとに春分の日が異なるのかについても紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
春分の日の由来

「春分」は太陽の動きをもとに一年間を24つに分けた「二十四分節」のひとつです。そのなかでも春分は立春からはじまる4つ目の節。
名前の由来は、現在でもおこなわれている皇室の行事「春季皇霊祭(しゅんきこうりょうさい)」から。皇霊祭は歴代の天皇、皇族を祀られ、現在の皇族の方々も出席されることが多い宮中祭祀です。
春分の日は祝日!なぜ休みなの?
それでは、なぜ春分の日は祝日となっているのでしょうか。これには、古くから春分の日には「春季皇霊祭」、秋分の日には「秋季皇霊祭」という宮中祭祀が執りおこなわれてきたことに由来します。
戦前の日本において、この2つの祭祀はとくに重要なものとされていました。そのため、さまざまな変遷がありつつも、1948年に「国民の祝日に関する法律」によって祝日に制定されたのです。
ちなみに同法律内で、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」、秋分の日は「先祖をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」として記載されています。
春分の日が持つ意味

自然をたたえ、生物をいつくしむ日
上述の通り、春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」という意味を持ちます。暖かさを感じられる季節に、身の回りの自然と触れ合う時間をとろう、という願いが込められているのだとか。
もともと二十四節気は農作業のスケジュールを見極めるために生まれたものだともいわれています。そのため、春分を目安に農作業を本格的にスタートすることもあるそう。自然を相手にする農業にとっても、春分は重要な日であるということですね。
先祖を供養する日
春分の日はご先祖さまを供養したり、お墓参りをしたりする日としても知られています。これは、春分の日が、お彼岸の中日にあたるからです。
お彼岸は春分の日や秋分の日を中日とした前後3日間、合計7日間のこと。仏教においてあの世とこの世がもっとも近づくと時期とされています。そのため、現代においてもこの期間にはお墓参りに行ったり、仏壇にお供えをしたりします。寺院においては彼岸会という法要がおこなわれることもありますよ。
春分の日にやること
春分は自然をいつくしむという意味を持つ日。そのため、大きな自然公園、海、山や川などに出向くのもいいですが、何も特別なことをする必要はありません。気軽に近所の公園を散歩したり、花を飾ってみたりと、身のまわりにある自然に目を向けてみてはいかがでしょうか。
また、春分はお彼岸の期間中なので、余裕がある場合は家族そろってお墓参りに行くとよいでしょう。仏壇があるお家では、ご先祖さまや故人にお供えをするとより丁寧です。お墓参りに行くことができない場合は、手を合わせて故人を尊ぶ時間をとるのもよいでしょう。
春分の日はなぜ毎年違う?決まり方と春分の日一覧

春分の日は年によって3月20日だったり、3月21日だったりと一定ではありません。この違いは何が原因となっているのでしょうか。そのヒントは、「地球と太陽の関係」にあります。
ご存じの通り、地球は自転をしながら太陽のまわりをまわっています。これを公転といい、ほぼ同じ日に同じ場所を通って一周するのが特徴です。
ただし、地球が太陽の周りを公転する周期はぴったり365日なのではなく、厳密には365日と約6時間ほどかかるそう。そのため、国立天文台が観測をおこない、毎年春分の日がいつなのかを決めています。
春分の日一覧
じつは春分の日は計算で予測することができます。以下、2030年までの日程はあくまで予測ではありますが、今後の参考になさってくださいね。
・2023年:3月21日(火)
・2024年:3月20日(水)
・2025年:3月20日(木)
・2026年:3月20日(金)
・2027年:3月21日(日)
・2028年:3月20日(月)
・2029年:3月20日(火)
・2030年:3月20日(水)
春分の日・秋分の日の関係

秋分の日は春分の日と同じく国民の祝日にあたり、昼と夜の長さがまったく同じになる日でもあります。この日を境にして、昼の時間は徐々に短くなり、季節が秋から冬へと変わっていくのです。
春分の日は毎年3月20~21日頃ですが、秋分の日は9月22日~23日頃。春分の日と同じく、秋分の日が何日になるかは国立天文台の報告によって決まっています。
また、先ほどもお伝えしたとおり、春分の日と秋分の日はお彼岸の中日。そのため秋分の日にもお墓参りや仏壇へのお供えをして、先祖供養をおこないます。春分の日・秋分の日はどちらも気候が安定するので、おでかけをしたりお墓参りに行ったりするのにうってつけです。
春分の日の食べ物

ぼたもち
彼岸の日に食べるとよいとされている、ぼたもち。春の花である牡丹がもとになって作られたもので、漢字では「牡丹餅」と書きます。秋のお彼岸に食べるものは「おはぎ」と呼ばれますが、どちらもあんこともち米を使ったお菓子です。小豆に「邪気を払う」という意味があることから、ご先祖さまに備えるものという認識が広がりました。
赤飯
春分の日には赤飯が食べられることも。赤飯にもぼたもちやおはぎ同様、小豆に込められた「邪気払い」「魔除け」「厄除け」という意味があるとされています。家族や親戚がそろった席で用意すると、華やかな雰囲気を演出できそうですね。
彼岸そば・うどん
そばに「五臓六腑の汚れを清める」という意味があることから、お彼岸にはそばやうどんを食べる風習があります。具材に肉や魚は使わず、油揚げや野菜などを使うことで、仏教行事にふさわしい精進料理に。そばやうどんは消化がいいので、季節の変わり目で体調を崩しやすい春分の日にもぴったりです。
つくし
春になると地面から顔を出すつくしは、やわらかく、春を代表する食材として知られています。春らしさを感じられるため、春分の日に食べるのにうってつけ。お浸しやきんぴらにして食べるのがおすすめですよ。
はまぐり
桃の節句(ひな祭り)でも食べられることの多いはまぐりは、春分の日にも食べられることが多いです。縁起物として知られていて、対になっている貝殻がぴたりと合わさることから、良縁を願うという意味が込められています。
ふき・ふきのとう
つくしと同じく春の代表食材であるふき・ふきのとう。ふきのとうは、ふきの花のつぼみのこと。花のつぼみを食べられるのは、春先だからこそ。ふきは煮物に、ふきのとうは天ぷらにして食べるとおいしいですよ。ふきのとうのちょっぴり苦い味わいはクセになります。
春分の日は自然にふれ故人を尊び、心穏やかに過ごそう
日本の歴史や仏教と深い関わりを持つ春分の日。朗らかな日差しが暖かく、春の訪れを感じることができる日です。ぜひ、身のまわりの自然をいつくしみ、ご先祖さまを尊び、心穏やかに過ごす一日にしてくださいね。
阪急の「春のおいしいお取り寄せ」特集
桜や苺を使ったスイーツや旬のフルーツがラインアップ!
「春のおいしいお取り寄せ」特集はこちら
※商品情報や販売状況は2025年02月08日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介
食ナビチャンネル
-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説
食ナビチャンネル
-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方
食ナビチャンネル
-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介
贈りものナビ隊
-

暑い季節に食べたい!夏に映える和菓子の魅力
sara
-

「水無月」の魅力とは?ういろうとの違いや6月30日に食べる理由も解説
sara
-

行事食とは?年中行事の料理や食べ物の意味・由来を一覧で紹介
食ナビチャンネル