
ライフスタイル&ヘルス2023/2/28 更新
お彼岸のお供えの定番は?金額相場や贈る際のマナーも紹介
お彼岸には、お墓や仏壇にお供えをするのが一般的です。お彼岸のお供えには、どのようなものが適しているのでしょうか。この記事では、お彼岸のお供えの定番品を紹介します。お供えを贈るときのマナーやお返しについても解説するので、参考にしてください。
お彼岸とは

春と秋の年2回訪れるお彼岸は、感謝の気持ちを込めてご先祖様を供養をする仏教行事です。
春のお彼岸は、3月の春分の日を中心とした前後3日、合計7日間のことであり、「春彼岸」と呼ばれます。秋のお彼岸である「秋彼岸」は、9月の秋分の日を中心に前後3日、合計7日間の期間です。この春分の日と秋分の日を、お彼岸の真ん中の日という意味で中日(ちゅうにち)といいます。
お彼岸はお墓の掃除やお墓参りをしたり、仏壇にお参りしたりして故人をしのびます。
お彼岸ではお供えをするのが一般的
お彼岸では、仏壇・仏具の手入れや掃除をして、お参りをおこないます。お墓をきれいに掃除をしてからお参りをおこない、親戚など他家を訪問することもあります。お参りや他家への訪問には、お供えを持参することが一般的です。
【実家・自宅】お彼岸で定番のお供え一覧

お彼岸に欠かせないお供えには、いくつかの定番品があります。ここからは、自宅の仏壇や実家のお墓参りに持参したい、定番のお供えを紹介します。
ぼた餅・おはぎ
お彼岸といえば、ぼた餅とおはぎを思い浮かべる人が多いでしょう。春彼岸には、春の花である牡丹にちなんだぼた餅を、秋彼岸には萩に由来したおはぎをお供えします。餅を包み込むあんこに使われている小豆には、魔除けの意味が込められていますよ。
花
毒やとげがあるもの、香りが強いもの以外であれば、お供えの花はどのようなものでもかまいません。菊・百合・蘭・カーネーションなどが年間を通した定番ですが、季節の花や故人が好きだった花でもよいでしょう。
果物
長期間お供えをしても傷まないように、季節の果物のなかから比較的日持ちする果物やまだ熟していない固めの果物を選びましょう。りんごや柿、ぶどう、メロンなどの果物が人気です。丸い形を表す「円」が「縁」に通じるため、丸い果物がよいとする風習もあります。
精進料理
仏教の教えに従って肉や魚介類を使わず、野菜や穀類、豆類など植物性の食材のみを使用して作った料理を精進料理といいます。お彼岸は仏教行事なので、精進料理をお供えすることもありますよ。お彼岸のお供えにする精進料理の献立は一汁三菜が基本で、「御料具膳(おりょうぐぜん)」という専用のお膳に盛り付けてお供えするのが通例です。
【他家へのお参り】お彼岸で定番のお供え一覧

お彼岸では、親戚などの他家へ訪問してお参りすることがあります。その際にも、手土産としてお供えを持参したほうがよいでしょう。ここからは、他家へお参りするときに持って行きたい、定番のお供えを紹介します。
菓子折り
日持ちのするお菓子も、お彼岸のお供えの定番です。個別に包装されていることが多い、まんじゅうやせんべいなどの和菓子、クッキーやマドレーヌといった洋菓子がお供えにおすすめ。ゼリーや缶ジュースは賞味期限が長いため、贈られる相手も受け取りやすいでしょう。
進物線香・ローソク
お菓子以外でお供えにおすすめなのは、線香やローソクです。お供えには、普段使用する線香とは異なる、きれいに包装されて箱に入った「進物線香」を選びましょう。線香と同じものと考えて、ローソクでもかまいません。線香やローソクは使うとなくなる消え物なので、贈られた相手が持て余して困ってしまうことも少ないでしょう。
花
自宅の仏壇や実家のお墓参り同様、他家を訪問する際もお供えとして花を持参してかまいません。派手な色の花は控えて、白色や淡い色の花を選ぶとよいでしょう。すでに花を飾っていて花器がない場合があるので、バスケットなどに生けられたアレンジメントの花がおすすめです。
現金(香典)
物品の代わりにお供えする現金を香典(こうでん)といい、水引が付いた香典袋や不祝儀袋に入れて渡します。香典に包むお札の枚数が偶数だと、マナー違反とされるので注意しましょう。香典は、品物と合わせて贈ってもかまいません。
お彼岸のお供えの金額相場は?
お彼岸のお供えとひと言でいってもさまざまなものがありますが、その金額相場は香典・物品共通して3,000〜5,000円程度とされています。現金と品物を一緒にお供えする場合は、合わせて5,000円以内に収まる程度が妥当です。
関わりが深かった故人へのお供えは、金額を若干高めにすることがあります。しかしその場合でも、1万円程度までに収めるのがよいでしょう。あまりに高額なお供えを持参すると、相手の負担になる場合があります。紹介した金額相場を目安にして、お供えを選んでみてください。
お彼岸のお供えはいつからいつまでにする?

お彼岸の期間は、春分の日や秋分の日を中日とした合計7日間とされていますが、お供えのタイミングはお供えする方法により異なります。お彼岸のお供えをする時期を、お供えの注意点と合わせて紹介します。
仏壇にお供えする場合
仏壇には、お彼岸の初日にお供えして、最終日にお供えを下げるのが一般的です。食べ物など傷みやすいものの場合は、お彼岸の中日に当たる春分の日や秋分の日を中心にお供えしてください。
お供えは「高杯(たかつき)」や「盛器(もりき)」といった、お供え用の器を使いましょう。これらの器は足が高くなっており、仏様への敬意を表せるといわれています。菓子折りなどはそのままのせてかまいませんが、果物の場合は果汁が出てきたときに安心なように、三角に折った半紙を下に敷くとよいでしょう。
他家へ手土産として持参する場合
お彼岸の期間中であれば、お供えをいつ持参しても問題ありません。しかしお彼岸の時期はお墓参りに出掛けていたり、自宅で法要をおこなったりと、相手が忙しくしている場合があります。そのため、訪問前に相手へ連絡を入れておくのが無難です。お彼岸の期間中に訪問するのがむずかしいときは、お彼岸の前に訪ねるようにしましょう。
他家へお供えを郵送する場合
どうしても都合が合わない場合は、お供えを郵送してもかまいません。お彼岸の初日、もしくは中日の春分の日・秋分の日までには相手のもとに届くように手配しましょう。その際、お供えの品を郵送したことを相手に知らせておくと、受け取りがスムーズにおこなえます。
お彼岸のお供えを郵送する際の注意事項
お供えを郵送する際には、いくつか注意が必要です。ここから紹介するポイントをおさえて、滞りなく相手が受け取れるようにしておきましょう。
現金(香典)を一緒に送る場合は「現金書留」で
お供えと一緒に現金を送る場合は、必ず日本郵便の「現金書留」を利用してください。現金書留専用の封筒にお金を入れて送ると、万が一届かなかったときに金額を賠償してくれるので安心です。
香典で現金書留を利用するときは、専用封筒にそのまま現金を入れるのではなく、必要事項を記入した香典袋に入れてから専用封筒に収めましょう。
手紙を添える場合は「信書便」を使う
品物だけを送るよりも、手紙を添えると気持ちまで相手にきちんと伝わります。デパートなどで購入したお供えに、自分で書いた手紙を入れて送りたい場合は「信書便」を使うことに注意してください。
信書便を使用しないと、場合によっては法律に抵触する可能性もあります。手紙を同封したい場合は、事前にお店のスタッフに相談しておくとよいでしょう。
掛け紙・香典袋のマナー
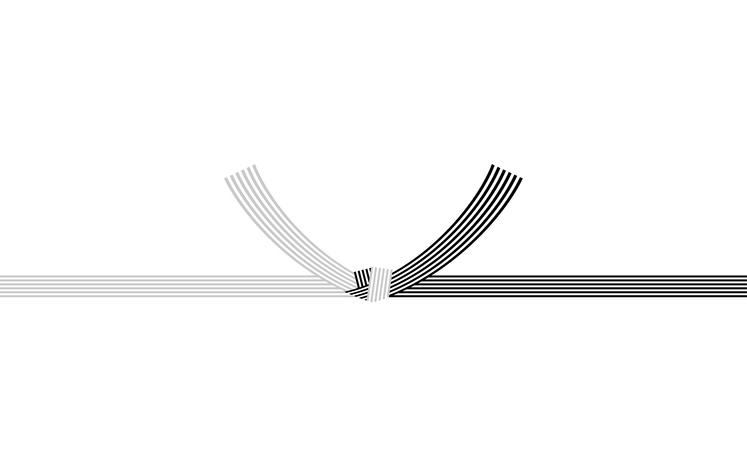
お彼岸だけでなく、弔事のお供えには水引が付いた「掛け紙」をかけて贈るのが一般的とされています。お供えとして現金を贈るときに使用する香典袋にも、選び方や書き方にマナーがあります。いざというときに困らないように、掛け紙や香典袋の作法を確認しておきましょう。
掛け紙の選び方・付け方
弔事のお供えには、白黒または双銀と呼ばれる銀色の水引が付いた掛け紙を使用します。弔事の水引は、二度と繰り返さない意味を込めて、固く結ばれた「結び切り」を選びましょう。もともと水引は、掛け紙の上からヒモのようにかけて結ぶものでしたが、現在は水引が印刷された掛け紙を使うのが一般的です。
誰からのお供えかがすぐにわかるように、お供えの包装紙の外側に掛け紙をかけるのがよいでしょう。
表書き・名入れの仕方
掛け紙には「御仏前」または「御供」と記入し、その下にお供えを渡す側の名前をフルネームで記しましょう。記入はボールペンではなく、濃い色の筆や筆ペンで書くことがマナーです。
香典袋の選び方
現金をお供えする場合は、白黒または双銀の結び切りの水引が付き、白無地または蓮の花が描かれた「香典袋」または「不祝儀袋」を使用します。
表書きや金額・連絡先の書き方
香典袋と不祝儀袋は、中袋と外包みに分かれているタイプが一般的。外包みの表面には「御仏前」または「御供物料」と書き、その下に濃い色の筆や筆ペンで、香典を渡す側の名前をフルネームで記入しましょう。
中袋の表面には入れた金額を、旧字体の漢数字で記入します。裏面の左下に、渡す側の住所と氏名を書いてください。中袋がないタイプの香典袋であれば、外包みの裏面に金額・住所・氏名を記入してかまいません。
お彼岸のお供えにお返しは必要か
お彼岸のお供えは身内からもらうことが多いため、お返しは不要とされています。ただし、感謝の気持ちを表したいなどの考えがある場合は、お返しをしてもかまいません。
お彼岸のお供えにお返しをするときは、タオルや洗剤などの日用品や、海苔やお茶といった消え物がよいでしょう。相手に好きなものを選んでもらえる、カタログギフトも人気です。
お返しの金額は、贈られたお供えの3〜5割程度が相場です。お返しを贈る場合、お供えをいただいたら、できるだけ早いタイミングで渡すようにしましょう。
マナーに従ってお彼岸のお供えを用意しよう
故人をしのぶお彼岸では、お供えをするのが一般的。お彼岸のお供えは花や果物、菓子折り、香典などが定番とされています。お供えには金額相場やマナーがあるので、事前によく確認して準備するようにしましょう。
※商品情報や販売状況は2023年02月28日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

行事食とは?年中行事の料理や食べ物の意味・由来を一覧で紹介
食ナビチャンネル
-

【非常食のレトルト活用法】おすすめ商品・備蓄のコツ・ポリ袋炊飯方法も紹介
贈りものナビ隊
-

グルテンフリーとは?意味やメリットを管理栄養士が簡単に解説
小嶋絵美
-

残暑見舞いっていつまで?送る側のマナーや贈り物の一般例も紹介
食ナビチャンネル
-

十五夜とはいつ?由来・時期・お供え物など基本情報を解説!月見団子のレシピ付き
食ナビチャンネル
-

父の日に贈る花といえば?阪急百貨店おすすめの人気・定番フラワーギフト7選
贈りものナビ隊
-

父の日におすすめのギフト35選!人気の品からおしゃれなものまで
贈りものナビ隊
-

【予算別】喜ばれる父の日ギフトとは?相場や選び方のポイントもご紹介
贈りものナビ隊
-

2025年(令和7年)の父の日はいつ?発祥の由来や各国の過ごし方を解説
食ナビチャンネル
-

2025年の父の日をチェック!由来やおすすめギフトも
贈りものナビ隊






