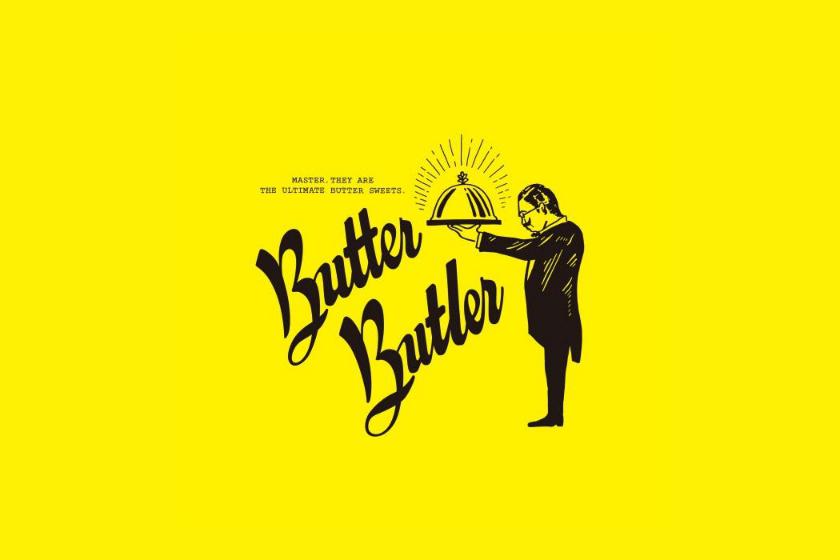ライフスタイル&ヘルス2024/5/8 更新
お香典の相場は関係性や地域・葬式の種類によって異なる!包む金額の目安やタブーな金額を紹介
故人の供養という意味のほか、遺族の急な出費の負担を軽くするという意味もある「香典」。香典は、年齢・葬式の種類・故人との関係性などで金額が異なります。そこでこの記事では、香典の相場や、葬儀別の香典の渡し方などを紹介します。
葬儀のお香典の相場はいくら?
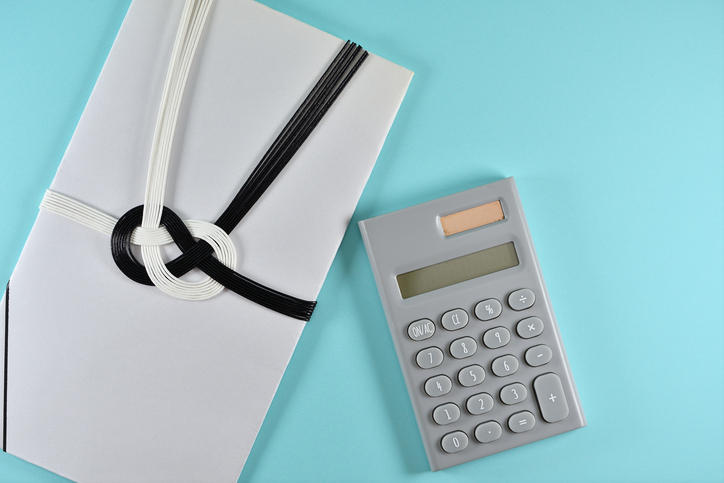
「通夜や葬儀でかかる費用の助け合い」という意味が込められている香典。その金額は一定ではなく、年齢・故人との関係性・葬儀の種類などによって異なりますが、なかでも金額に大きな影響を及ぼすのが"故人との関係性"です。
また、香典は通夜・葬儀だけでなく、法要や法事ごとにも持参することが一般的。法要・法事に持参する際は、葬儀時に包んだ香典の半分の金額がマナーとされています。
【関係別】葬儀のお香典の相場

香典の相場を左右する"故人との関係性"。なかでも親族が亡くなった時には、相場が大きく変わります。そこで以下では、関係別の相場を詳しく紹介します。
親族|お香典の相場
親族のうち、両親の場合は50,000〜100,000円が一般的ですが、ご自身が20代の内は、30,000円〜100,000円の間で包むと良いでしょう。兄弟・姉妹の場合は30,000〜50,000円の間で、祖父母の場合は10,000〜50,000円の間で包むのがベターです。おじ・おばの場合は、多くの人が10,000円を包みますが、親しい関係であった場合は30,000円程度を包むこともあります。
両親......50,000〜100,000円
兄弟・姉妹......30,000〜50,000円
祖父母......10,000〜50,000円
おじ・おば......10,000〜30,000円
義両親......50,000〜100,000円
その他の親戚......5,000〜10,000円
友人・知人|お香典の相場
友人の場合は、5,000〜10,000円が相場です。ご自身が20代であれば5,000円を、30〜40代以上であれば10,000円程度を目安とすると良いでしょう。一方、習いごとの先生・近所の方などの知人であれば、3,000〜10,000円が一般的。特にお世話になった方の場合は、10,000円以上を包むこともありますが、10,000円を目安とするのがおすすめです。
友人......5,000〜10,000円
知人......3,000〜10,000円
職場関係者|お香典の相場
職場関係者のうち、上司の場合は5,000〜10,000円を目安としましょう。上司の家族や同僚の場合も同様です。一方、同僚のご家族の場合は、知人と同じく3,000〜10,000円がベター。あまりにも高い金額は、相手に気を遣わせてしまうおそれもあるため、参列する会社の方々とも話し合って決定するのがおすすめです。
上司・その家族......5,000〜10,000円
同僚......5,000〜10,000円
同僚の家族......3,000〜10,000円
法事(法要)のお香典の相場

読経や焼香などの儀式を指す「法要」に対し「法事」は"四十九日・一周忌・三周忌・七周忌などにおこなわれる、法要後の会食まで"の一連の行事を指す言葉です。そんな法事の相場は前述した通り、葬儀の際に包んだ香典のおおよそ半分の金額。両親の葬儀に包む香典は50,000〜100,000円なので、法事には30,000〜50,000円を包むと良いでしょう。
葬儀のタイプによってお香典の金額や渡し方は異なる

葬儀には、一般葬・家族葬・一日葬・直葬など、多くの葬儀形式があります。「一般葬」では多くの参列者を招待する一方で「家族葬」はごく身近な人たちだけで執りおこないます。一般葬では香典を持参しますが、家族葬では香典・供物・供花を辞退される場合も多いため、ご家族の申し出に合わせるようにしましょう。
通夜をおこなわず告別式と火葬のみをおこなう「一日葬」、通夜・告別式をおこなわず火葬のみをおこなう「直葬」は、一般葬と同じく、香典を持参するのがマナーです。香典の金額も、一般葬と同じ金額で用意しましょう。
上記は仏教の場合の渡し方ですが、相手がキリスト教の場合は「御花料」として、神道の場合は「御神前」などとして用意します。相場は仏教と同じ金額で用意するのがベターです。
お香典のタブーな金額とは

iStock.com/Atstock Productions
タブーな金額には、多すぎる金額・忌み数・偶数があります。多すぎる金額には「お金が重なる=不幸が重なる」という意味があり、縁起が悪いとされるため控えるのがベターです。忌み数と言われる4と9は「死」や「苦」を、偶数は「割り切れる=縁が切れる」と捉えられることがあるため、これらも避けておくのが良いでしょう。
葬儀のお香典に関するよくある質問
香典を辞退されている場合はどうすれば良い?
香典辞退をされた場合は、基本的に香典を持参する必要はありません。しかし故人が親族の場合は、喪主やご家族に直接確認すると良いでしょう。
家族葬でお香典を渡すタイミングはいつ?
香典を渡すタイミングは、"告別式に参列する際"です。通夜は"家族や親族が故人を偲ぶ時間"とされているため、多くの人が集まる告別式で渡すのがおすすめ。もしも「通夜にしか参加できない」という場合には、ご家族にお悔やみの言葉を添えて渡すと良いでしょう。
葬儀に参列できない場合はどうやって渡す?
通夜や告別式に参列できない場合には「代理を立てる」「郵送する」「後日弔問する」という方法があります。代理人は故人と面識がなくても問題ありませんが、本人の出席できない理由を事前に伝えておくと丁寧です。郵送する場合は現金書留でおこない、後日弔問する場合は事前に予定を確認してから赴くようにしましょう。
お香典の相場は"故人との関係性"が肝
「費用の互助」の意味合いを持つ香典の相場は、親族・友人・職場関係者など、故人との関係性によって大きく左右されます。一般的に、特に近しい親族である場合は、より大きな金額を包む傾向にあります。一方、多額・忌み数・偶数といった、包んでしまうと失礼にあたる金額もあるため、香典を包む際にはぜひこの記事を参考にしてみてください。
※商品情報や販売状況は2024年05月08日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力
sara
-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説
秋山 ちとせ
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介
食ナビチャンネル
-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説
秋山 ちとせ
-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介
食ナビチャンネル
-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説
食ナビチャンネル
-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方
食ナビチャンネル