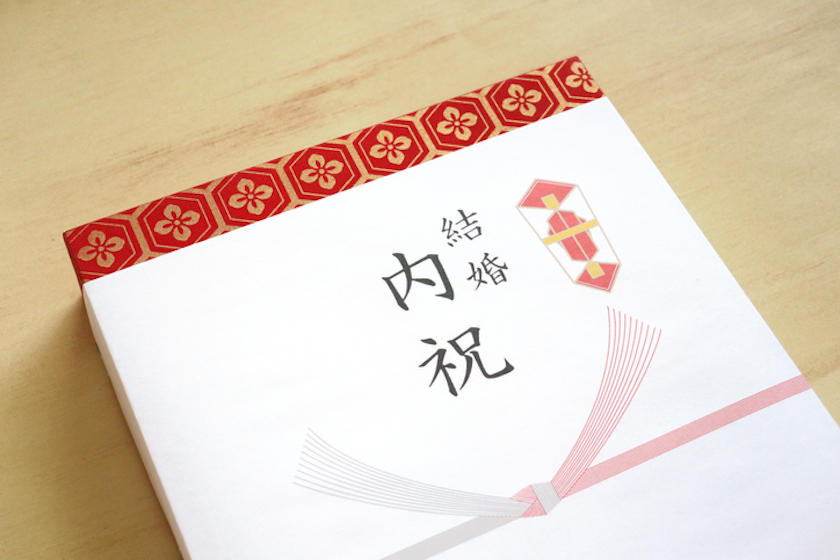
ライフスタイル&ヘルス2022/3/12 更新
内祝いはいつまでに贈るべき?タイミングやマナーを詳しく解説!
内祝いとは、結婚や出産などの際に、お祝いを頂いた方にお返しを贈る習慣のこと。内祝いはいつまでに贈るのが適切か悩んだことはありませんか?この記事では、内祝いを贈る時期、贈るときのマナー、内祝いに困ったときの対処法についてご紹介します。
内祝いはいつまでに贈ればいい?
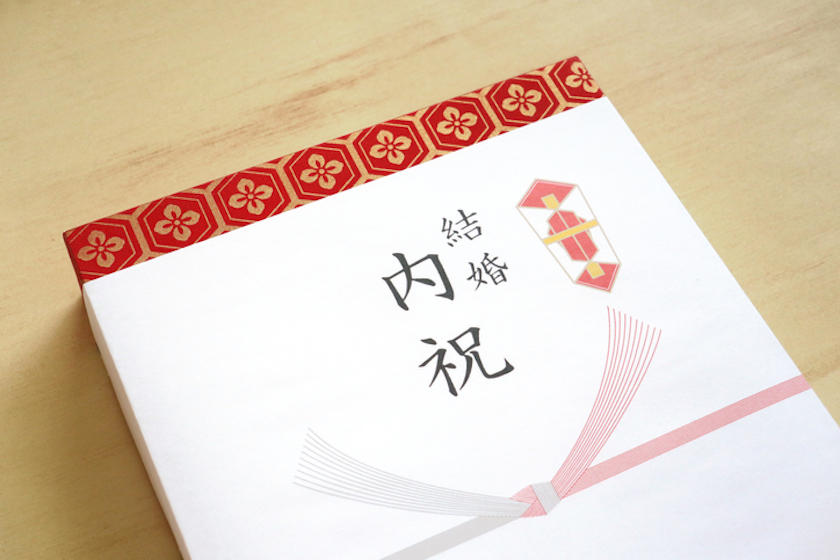
本来、内祝いとは、身内のなかで起こった喜びのお裾分けとして贈り物をすること。しかし現在では、お祝いを頂いた方にお返しをする習慣のことをさします。
内祝いを贈るタイミングは、結婚や出産、新築、退院など、内容によって異なります。一般的には、お祝いを頂いてから1ヵ月以内が目安。遅れそうなときは、相手にお伝えしてできる限り早く手配するようにしましょう。
【内祝い別】お返しを贈る時期の目安

結婚内祝い
結婚内祝いは、お祝いを頂いてから1ヵ月以内に贈るのが目安です。結婚祝いは結婚式の前後に頂くことが多いため、結婚式後1ヵ月以内に内祝いを贈ることがマナー。また、結婚式後にお祝いを頂いたり、結婚式を挙げなかったりする場合は、頂いてから1ヵ月以内にお返しの品を贈るとよいでしょう。
結婚式の前に入籍をする場合、入籍時に結婚祝いを頂くこともあります。この場合も、結婚式後に内祝いを贈って問題ありません。しかし、入籍と結婚式まで随分と日が空いてしまう場合は、あらかじめ先方に内祝いが遅くなることを伝えておきましょう。
出産内祝い
出産祝いは、生後1週間から1ヵ月以内に頂くことが一般的です。そのため出産内祝いは、生後1ヵ月に迎えるお宮参りの頃までには贈るようにしましょう。遅くとも生後2ヵ月頃までに贈るのがマナー。産後しばらく経ってから出産祝いを頂くこともありますが、そのような場合は、お祝いを頂いてから1ヵ月以内に贈ります。
出産後は体調の回復に時間がかかったり、慣れない育児に奮闘したりと、あっという間に時間が経ってしまい、出産内祝いを贈るのが遅くなってしまうことも。スムーズに手配できるよう、出産前に内祝いを贈る可能性がある方のリストと、贈る物のおおよその検討をしておくとよいでしょう。
新築内祝い
家を建てた際に新築祝いを頂いた場合は、お祝いを頂いた方を新居にお招きしてお披露目するのが一般的です。しかし、新築のお披露目ができなかったり、招待したい方の都合がつかなかったりする場合は、内祝いを贈りましょう。
新築内祝いは、引っ越しを終えてから2ヵ月以内に贈ります。新築祝いを頂いたら、できるだけ早く相手にお礼を伝えましょう。遅くとも翌日にはお礼状を出したり、お礼の電話をしたりするのがマナーです。引っ越し後は片付けに追われてしまいがち。お祝いを頂いた際に、相手の住所や頂いた品物のリストを作成しておけば、慌てずに内祝いの準備をすることができますよ。
快気祝い/快気内祝い
快気祝い・快気内祝いはどちらも、病気やケガをした人が入院中や療養中にお世話になったり、お見舞いに来てくれたりした方に贈るものです。快気祝いは病気やケガが全快して良くなった場合に、快気内祝いは病状が良くなったものの通院や療養が続く場合に贈ります。
快気祝いや快気内祝いは、退院後1週間から10日ほどで贈ることが目安とされています。地域によっては「2週間以内に贈る」などの風習があるので注意が必要です。退院後は体調が優れないこともあるかもしれませんが、退院後何ヵ月も経ってから快気祝いを贈ることは失礼にあたります。快気祝いには、病気やケガが回復したことを報告する意味もあり、遅くとも退院後1ヵ月以内には贈るようにしましょう。
内祝いを贈るときのマナー

内祝いの贈り方、水引や熨斗(のし)、金額の目安には基本的なマナーがあります。相手との良好な関係を保つためにも、内祝いは適切に贈ることが大切です。
贈り方
本来であれば、内祝いはお祝いを頂いた方に直接渡すことが理想とされています。しかし、体調がすぐれない、都合が合わない、相手が遠方に住んでいるなど、手渡しすることがむずかしいケースも。そのような場合は、無理をして内祝いを渡すことが遅くなるよりも、郵送したほうが失礼にあたりません。
水引や熨斗
内祝いを贈る際には、ふさわしい熨斗を選ぶようにしましょう。熨斗に印刷される水引は用途によって異なります。
結婚祝いや、快気祝い、快気内祝いには、「紅白結び切り」の水引を使います。結び切りは、一度結ぶと簡単に結び目がほどけないことから、一度きりであってほしいお祝い事に用いられます。水引の本数は通常5本または7本ですが、結婚内祝いは10本です。
出産内祝いや新築内祝いには、「紅白蝶結び」。蝶結びは、結び目が何度も結び直せることから、将来重ねて起こってもよいお祝いに用いられます。
金額の目安
内祝いの金額は、お祝いで頂いた金品の3分の1から半額程度が目安とされています。特に、高額なお祝いを頂いた場合は、半返しではなく3分の1程度の金額のものを選ぶようにしましょう。
内祝いの金額は相場に合わせたほうがよいとされています。高額すぎる内祝いは相手に余計な気をつかわせてしまうことも。逆に金額が低すぎても相手に失礼になってしまうので注意が必要です。
こんなときはどうする?内祝いに困ったときの対処法

内祝いを贈るのが遅れてしまったり、相手が喪中であったり、内祝いを贈る際に困ったことが生じる場合もあります。どのように対処するのが適切でしょうか?以下で詳しくご紹介します。
お祝いを遅くに頂いたとき
結婚式のあとに結婚祝いを頂いたり、出産後しばらく経ってから出産祝いを頂いたり、お祝いを遅くに頂くことも。この場合は、お祝いを頂いてから1ヵ月以内を目安に内祝いを贈ります。遅い時期にお祝いを頂いても、きちんとお返しを贈るようにしましょう。
贈るのが遅れてしまったとき
結婚や出産、新居への引っ越しなど、お祝いを頂く前後は新しい生活に忙しく、内祝いの準備をすっかり忘れていたということもあるでしょう。
内祝いの手配が遅れてしまった場合は、できるだけ早くに贈るようにするのがポイント。遅れてしまったからといって、何もお返しをしないのはマナー違反です。内祝いを手配したら相手へ届く前に連絡し、内祝いを贈ったこと、遅くなってしまったことへのお詫びの言葉を伝えましょう。あわせて、内祝いの贈り物に、お詫びの言葉を添えたお礼状をつけるとより丁寧です。
相手が喪中のとき
相手が喪中であることがわかった場合、内祝いを贈るタイミングには配慮が必要です。一般的には故人が亡くなってから四十九日間は忌中とされます。少なくとも忌中期間は贈らないことがマナーです。
四十九日が過ぎたからといって、大切な人を亡くした悲しみが癒えるものではありません。相手の事情を十分に考慮し、相手が落ち着くまで内祝い贈るのを控えても失礼にはあたりません。まずは相手へのお悔やみを優先し、挨拶状などで感謝の気持ちを伝えるとともに、後ほどご挨拶の品を贈らせて頂くことを先に伝えておくと丁寧です。
内祝いを贈る際はマナーを確認しましょう
結婚や出産など人生の節目においてお祝いを頂いた場合は、相手への感謝の気持ちを表し、お返しとして内祝いを贈ります。内祝いを贈るタイミングは、お祝いを頂いてから1ヵ月以内が目安。熨斗の選び方や金額についてもマナーがあります。内祝いは、最後まで相手への心遣いを忘れることなく贈りたいものですね。
※商品情報や販売状況は2022年03月12日時点でのものです。
現在の情報と異なる場合がございますが、ご了承ください。
ライフスタイル&ヘルス 新着記事
-

パネトーネとは?イタリアのクリスマスに欠かせない伝統菓子の魅力
sara
-

マサラティーとは?チャイとの違いや作り方を紅茶専門家が解説
秋山 ちとせ
-

ハワイコーヒーの魅力を知ろう!種類・特徴・楽しみ方・選び方を徹底解説
食ナビチャンネル
-

千歳飴とは?由来や語源、地域ごとの形や楽しみ方などを解説
食ナビチャンネル
-

敬老の日を簡単解説!意味や由来、子どもと一緒に楽しむ方法も紹介
食ナビチャンネル
-

自分へのご褒美アイデア満載!メリットや上手な楽しみ方・実例も紹介
食ナビチャンネル
-

フレーバーティーってどんな紅茶?主な種類や特徴を専門家が解説
秋山 ちとせ
-

十五夜の由来とは?食文化や地域による食習慣の違い、おすすめレシピを紹介
食ナビチャンネル
-

お月見とはどのような行事?発祥の由来や楽しみ方について徹底解説
食ナビチャンネル
-

お月見のお供え物の意味とは?団子やススキの由来と正しい飾り方
食ナビチャンネル













